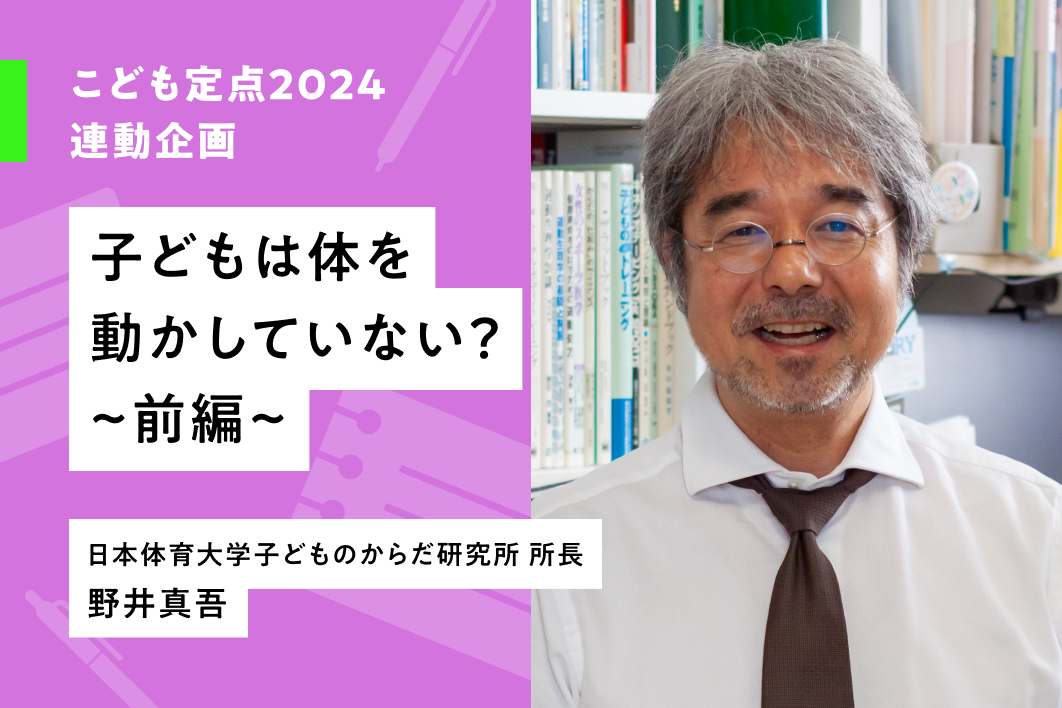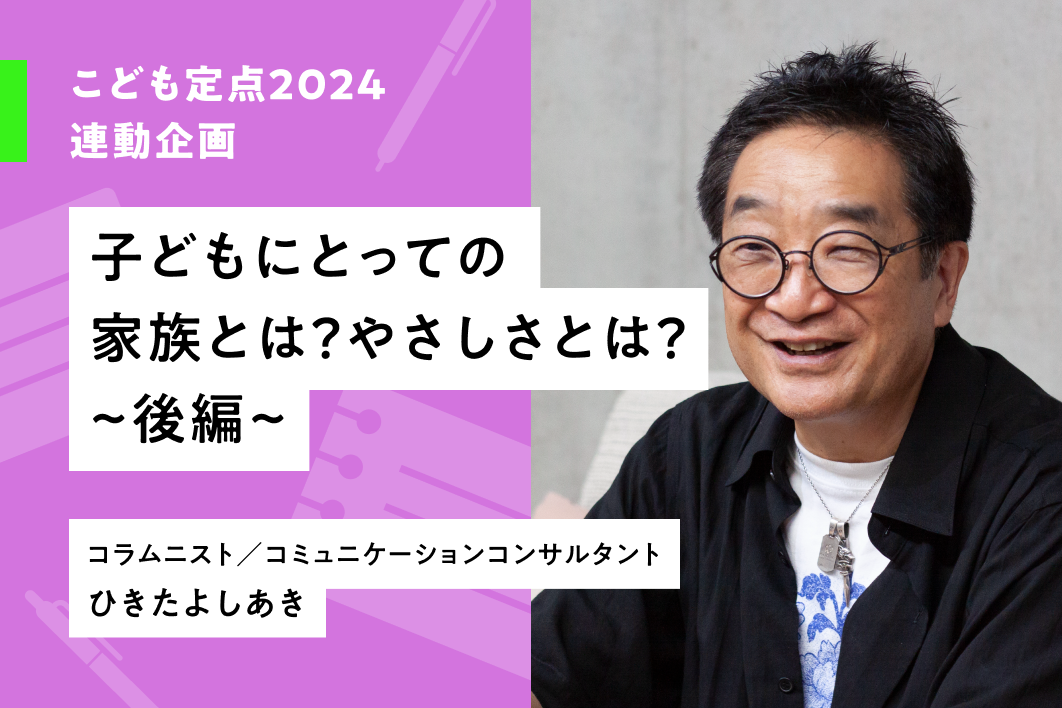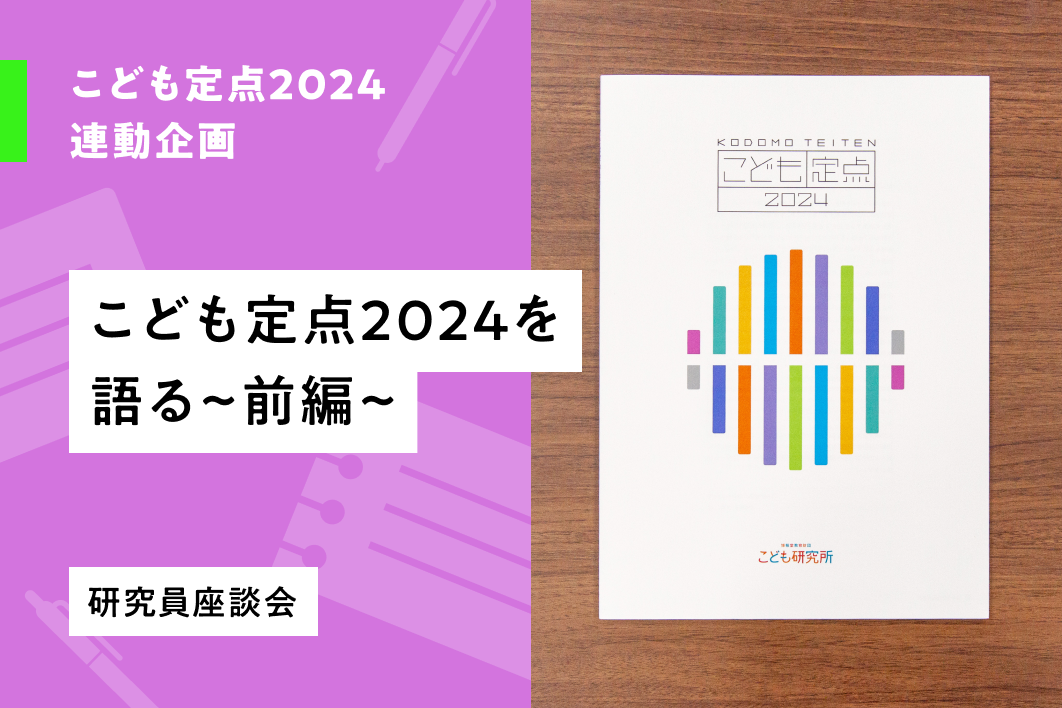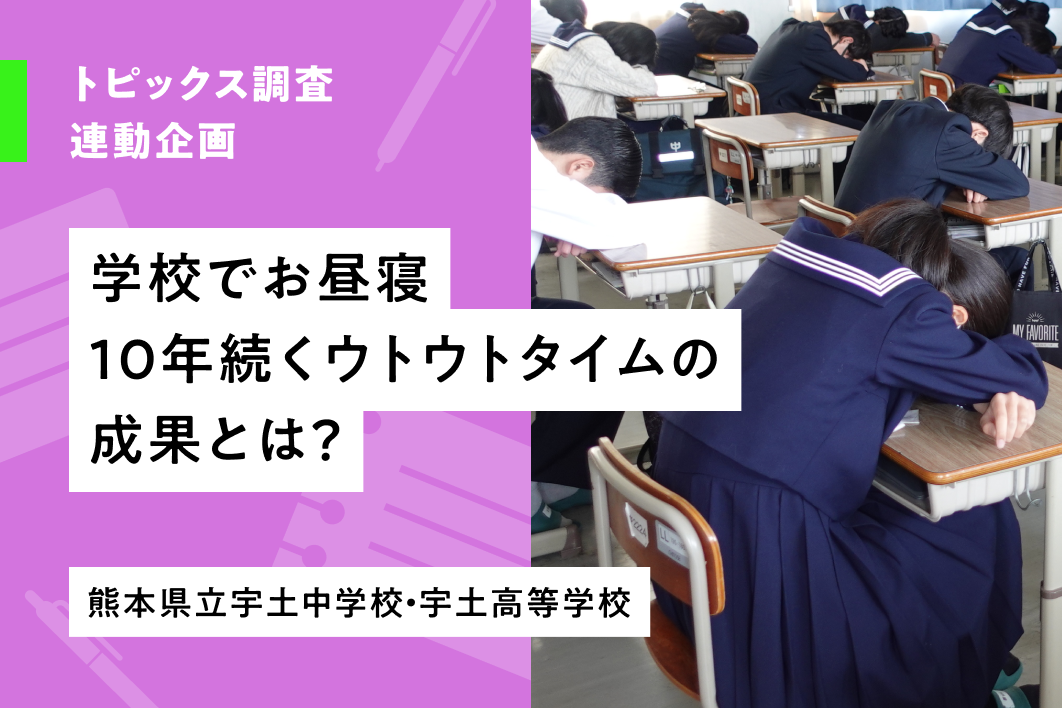子どもにとっての家族とは?やさしさとは? ~前編~
——大きくなる家族の存在感
コラムニスト/コミュニケーションコンサルタント・ひきたよしあきさんに聞く
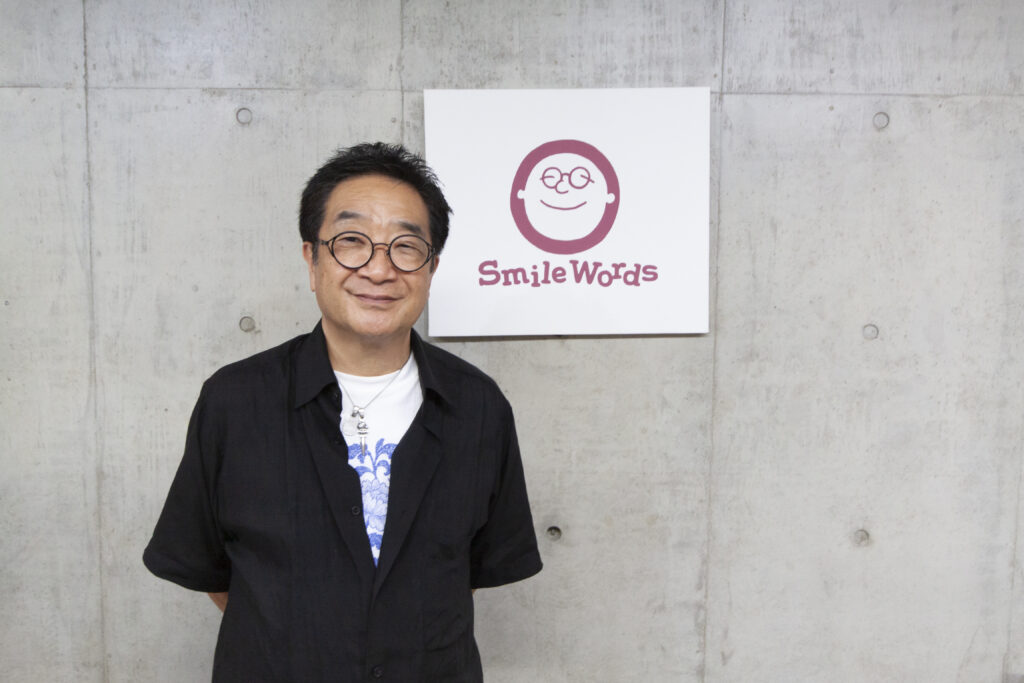
「こども定点2024」の調査結果をもとに、研究員が注目したキーワードから数字の奥に見える子どもたちの今を深掘りします。前編のテーマは、調査結果でも顕著だった“家族との関係”。 小学生への作文教育から大学での講義まで、子ども・若者の言葉の力を育む活動を続けるコラムニスト/コミュニケーションコンサルタント・ひきたよしあきさんにお話をうかがいました。
「動画」が日常になった、コロナ後の子どもたち
こども定点2024の結果をご覧になって、まずはどのような印象をお持ちですか。
まず感じたのは、この調査が“普通の子どもの姿”を表している、ということです。受験やいじめといったテーマやトピックスでは出てくるけれど、「今の普通の子どもがどうなのか」といった漠然としたテーマで調査したデータというのは、実は世の中にほとんどないんですよね。
全体を通してみると、やはりコロナ後の子どもたちの変化を感じます。この調査は2024年9月に実施されたとのことですが、コロナ禍を過ごした子どもたちにとっては、やはり「動画」が日常になっている。ここはすごく面白いところで、コロナによって、ソーシャルディスタンスが取られたり、iPadなどのタブレットを渡されたりした時期を経なければ、この結果にはなっていないでしょう。コロナ以後の変化としてみると、まさに時代の反映を感じますね。
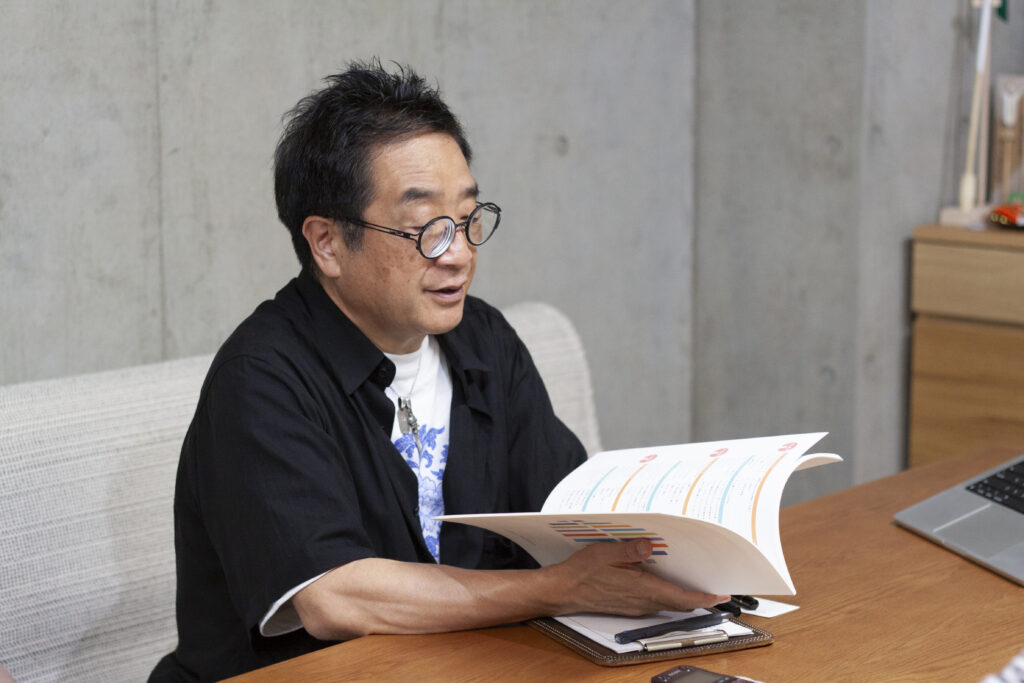
日頃、子どもたちと接するなかで、そういった変化を彼らの「言葉」や「表現」に感じることはありますか。
そうですね、今の子どもたちの間で特に弱くなっているのは「気持ちを表す言葉」です。自分の気持ちを細かく表現するのがすごく下手になっていて、例えば作文を書かせても、「遠足に行って楽しかった」までは書けるんだけど、それ以上書けない。
背景には、普段から動画を“見る側”にいて、自分から表現したりする機会が少ないことがあると思います。また、「やばい」「うざい」といった言葉でまとめてしまう傾向もあります。粗い語で何でも済ませてしまって、感情の因数分解ができない。
だから、学校の先生たちが工夫しているのも、気持ちを聞くことなんですよね。遠足について書くなら、「朝起きたときはどんな気持ちだった?」とか「友だちに会ったときはどうだった?」と細かく聞いて、感情を引き出すようにしているそうです。
子どもたちが感情表現しにくくなっている背景を、ひきたさんはどう見ていますか。
世の中が全体的に「タイパ」とか「コスパ」といったものを重視する風潮になっていますよね。共働きの家庭も多いから、両親ともに家でも“会社脳”で子育てをする傾向もあると思います。子どもが「今日ね、朝こんなことがあって、友だちに会ったらこうで……」なんて話し始めると、親もつい「で、なにが言いたいの?」と言ってしまう。
もちろん、動画に慣れ親しんでいるからこその、ポジティブな面もあります。例えばイラストを入れたりとか、自分で写真を撮ったりする時の感性は、我々の時代とは比べ物にならない。LINEのスタンプ一つにしても選び方にセンスがでたり、絵柄だけで通じ合うということがあったりもします。
そういう意味では、言葉にならない言葉というのが、子どもたちのなかですごく発達してきているんでしょう。言語力がないから表現能力が落ちているのではなく、表現手段が広がってきている、と見たほうがいい気はしてますね。
社会の影響という点では、子どもが大人のような言葉を使う場面も増えています。例えば、何かが欲しいときに親に“プレゼン”して買ってもらうといった風潮もありますね。
そうですね。「プレゼン」と同じように、最近は中学生が「ガクチカ」(※就活用語から出てきた言葉で「学生時代に力を入れたこと」の略語)なんて言葉を使うんですよね。
大人社会の言葉が子どもの社会にもどんどん入ってきているという傾向はあるでしょう。ただ、都会ではそうかもしれませんが、地方に行くと今でも自転車で走り回り、素朴な言葉で表現している子も少なくありません。
子どもの言葉や表現ひとつとっても「いまの子どもはこうだ」と一括りにはできないものがあります。地域や学校によって、それぞれが抱えている課題や問題意識も大きく異なってくるでしょうね。
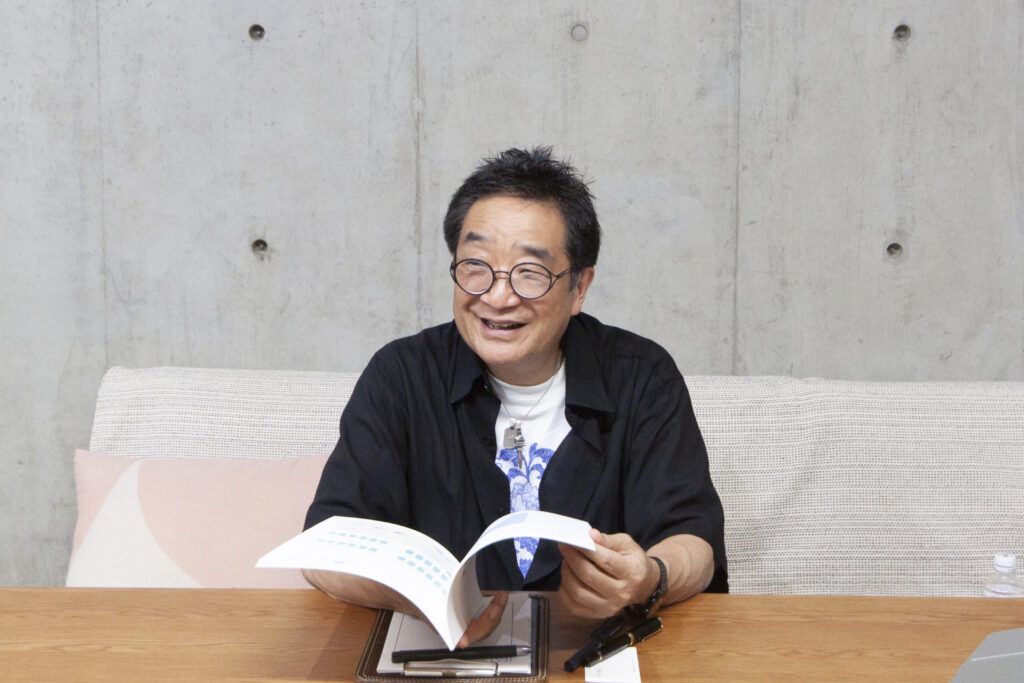
お母さんは人生のメンター、お父さんは?
そのほか、気になったポイントはありますか。
もう一つ、すごく興味深かったのは「お母さんがメンター」というところですね。これは、私自身もものすごく感じている点です。 お母さんの影響というか、とにかく子どもたちみんな、お母さんが好きなんですよ。
私は今大学でも教えていますが、学生の多くは結婚願望が乏しいんです。結婚したくない。理由を聞くと、「こんなにいいお母さん、家族がいるのに、今からわざわざ別の家庭をつくる必要あるのか」と。作文を書かせると、大学生になって一人暮らしを始めているので、みんなお母さんの偉大さに気づき、大好きがあふれているんです。
一方で、お父さんの順位は低いです。「参考にする人の意見」では、「お母さん」と答える割合が学年があがっても8割をキープしているのに対し、「お父さん」は中学3年生では6割程度にまで落ち込みます。
お父さんは、順位が「低い」というよりそもそも話に出てこない印象がありますね。笑い話ですが、「今日はお父さんが出張でいなかったので、家族で楽しく過ごしました」って書いてくる子もいます。
昔はお母さんが家を守り、お父さんは“社会の声”を代弁するようなところがありましたが、今は両親ともに高学歴だったり、給料だって両方稼ぐわけですから、世の中のことを詳しく話せるのは、コミュニケーション能力の高いお母さんのほうかもしれません。
調査では、「家族の一員だと感じる」子が89.5%、「一番大切なもの=家族」が71.9%。家族の存在感がすごく大きく出ている結果です。ただその場合も、お父さんをどの程度含んでいるか、人によって異なる可能性がありますね。あるいは、お母さんとの関係を「家族」と考えている可能性もありそうです。
ただ、基本的に家族が大好きという傾向は強いと思います。コロナ期に、家族で集まって過ごした経験が、帰属意識を押し上げたという背景はあるでしょう。
作文を見ても、家族で何かをしたという話が多いですね。バーベキューに行ったり、カラオケしたり、最近は家族同士で出かけるケースも増えています。学校や地域の枠を越えて、家族そのものが子どもにとっての最も安定したコミュニティになっています。
一方で、お父さんの役割や存在感が薄くなっているのだとすれば、子どもたちにとっての「お父さん像」が新たに必要になってくるのではないでしょうか。それをどう提示できるかが、これからの課題かもしれません。

頼れる家族、揺れる友だち関係
昔は、家族には反発するものという風潮がありましたが、今は逆に家族に向かう傾向が強いということなのでしょうか。
ひとつ考えられるのは、今の子どもたちにとって、学校という社会でストレスになるのは、身体的なわかりやすいいじめではなく、仲間はずれになったりハブられたりすることなんです。そうならないように、と気を張り続けて、表面的には仲良くして疲れて家に帰ってくる。
そうなると、唯一肩の力を抜ける場所が家族、と読みとける側面もありそうです。家に帰れば外で付けていた仮面を外して、ホッと安心できるという感覚が強いのでは。昔は、子どもの顔を見てお父さんもお母さんも心が安らいだけど、今は子どもがお母さんの顔を見て、「ああ、家に帰ってきたな」と感じている気がしますね。
それに、今の時代のお母さんは、気持ち的にも若いですよね。学生の母親からの手紙で、息子が私の授業がおもしろいというので、授業参観の希望をもらったことがあります。今や、お母さんの積極性が、いろんなところに波及しているんでしょうね。
お話を聞いていて、子どもたちの言葉や表現はまるで会社員のように大人化しているのに、実際の自立や大人になることは先延ばしになっているようにも感じました。
今や男子学生でも、お母さんから学んだりして料理もするし、ファッションから恋愛相談まで、あらゆる領域でお母さんが活躍している。悩み事は友だちには相談しないで、もう家族で解決する。お母さんは、親であり、友だちであり、ちょっと恋人みたいでもあり、とにかく総合力が高い存在です。
ただ、子どもたちの属するコミュニティもどんどん増えています。学校、塾、習い事、ネットやゲームなど、友だちの種類も広がっています。
これは地域差関係なく、リアルでもバーチャルでもそうで、「友だち」といっても、我々が想像する教室の中だけの友だちではなくなっています。その概念を広げておかないと、家族関係や自立も含めて、我々も見誤るところが出てきそうな気がします。

(後編につづく)