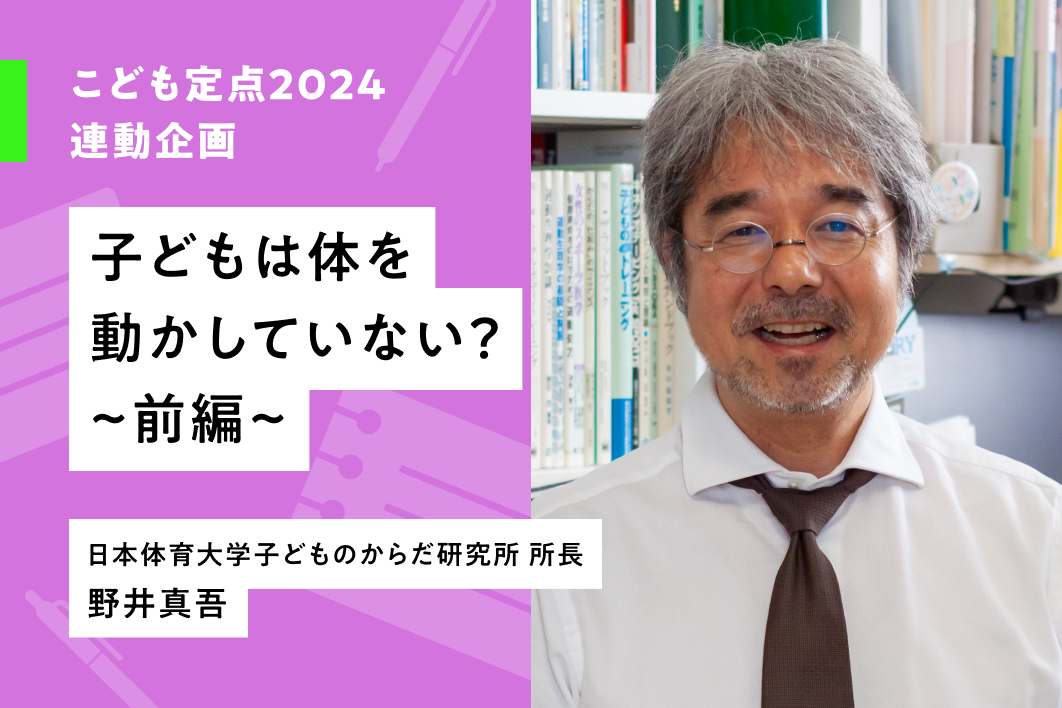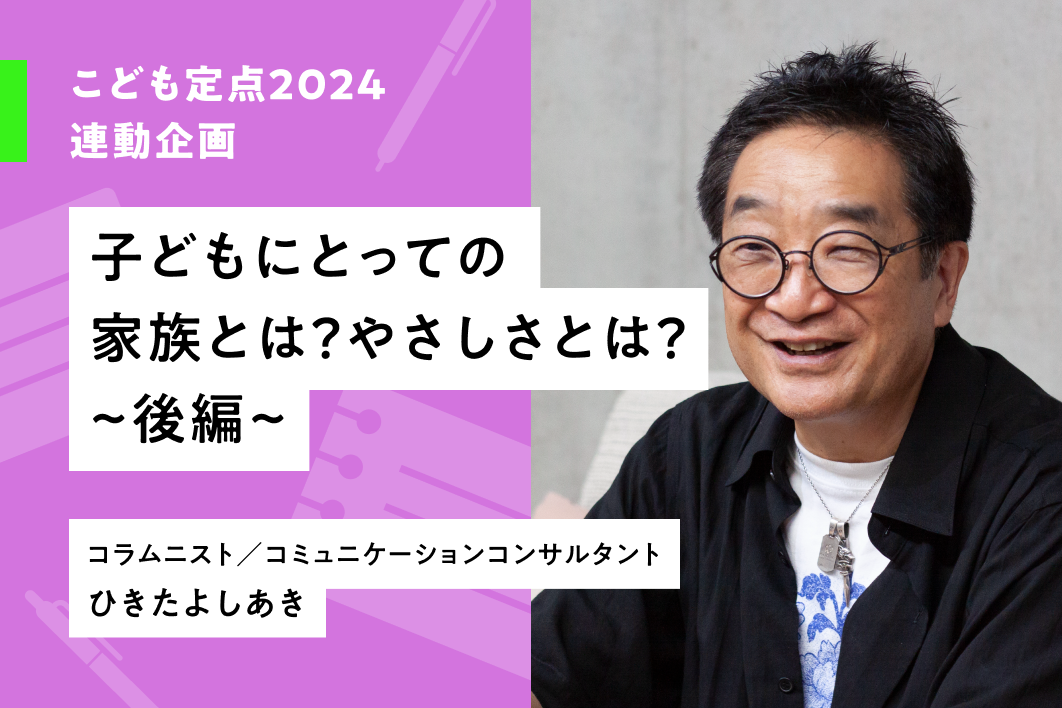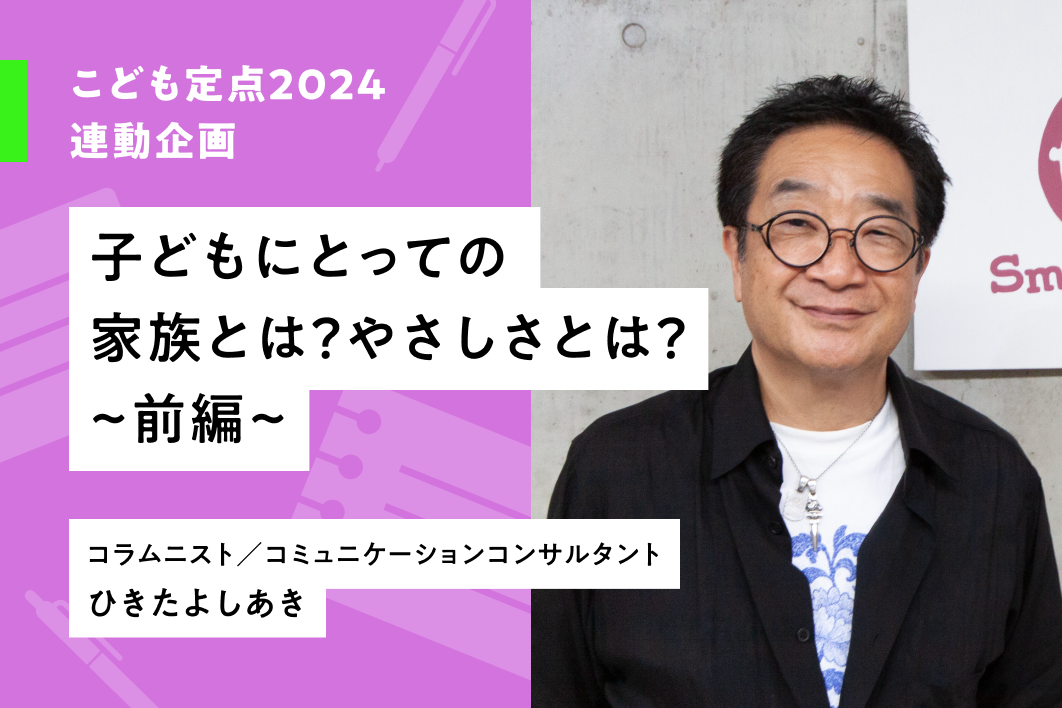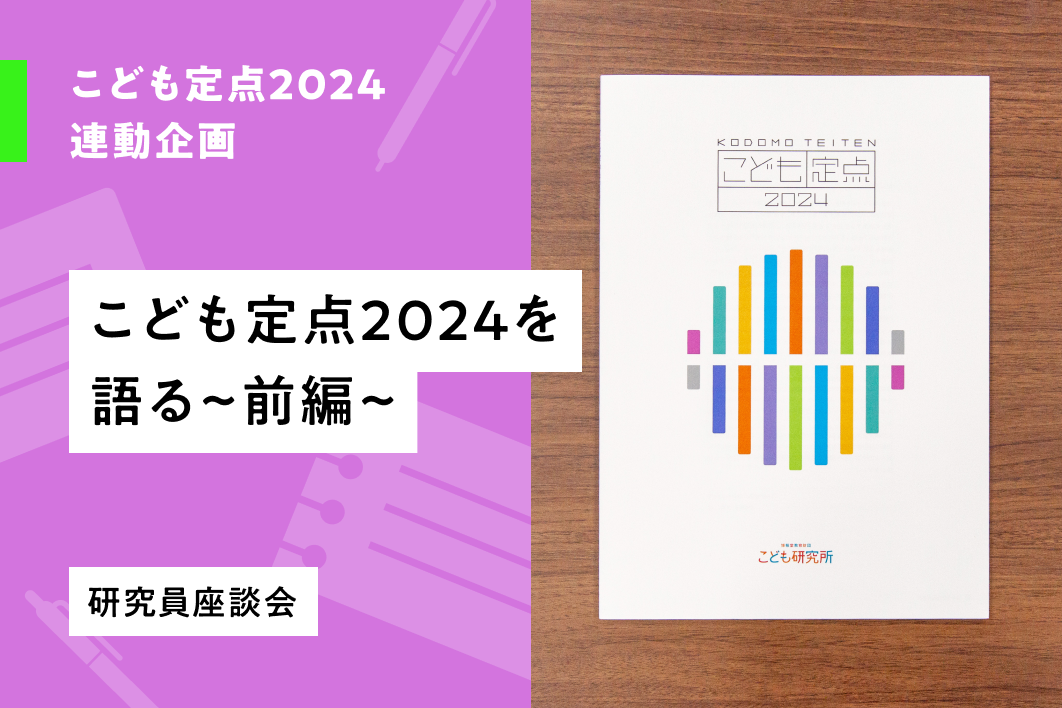学校でお昼寝 10年続く「ウトウトタイム」の成果とは
熊本県立宇土(うと)中学校・高等学校に聞く
トピックス調査「どのくらい眠ってる?」の結果では、子どもたちは睡眠の重要性を理解しつつも「もっと遅くまで起きていたい」という願望があることがわかりました。さらに「学校にお昼寝時間があるとうれしい」かどうか尋ねたところ、小学生の約半数、中学生の6割以上が「はい」と回答しました。そこで、今回はトピックス調査の連動企画として、10年以上前から昼食後にお昼寝時間を設けている熊本県立宇土中学校・高等学校を訪ねて、導入の経緯や成果についてお話をうかがってきました。

13時20分、教室のカーテンが閉じられ、生徒たちが一斉に机の上でうつ伏せになりました。昼食後、10分間だけ昼寝をする「ウトウトタイム」のはじまりです。先ほどまでのお昼ご飯を賑やかに楽しんでいる様子とは一変し、穏やかな音楽とともに静かな時が流れ始めました。
熊本県立宇土中学校・高等学校では昼休み後に10分間の昼寝時間「ウトウトタイム」を設けて11年目になります。午後の授業中に居眠りをする生徒が大幅に減少したほか、生徒からは「授業に対する集中力や意欲が向上した」という声があがっています。
中学2年生のクラスでお話をうかがいました。
「テスト前とか、授業のとき集中力が絶対に変わるなあ」

「ウトウトタイム」はいかがですか?
「ウトウトタイム」で寝ると頭がすっきりして、午後からの授業で集中しやすいです。
中学に入学した時は「ウトウトタイム」についてどう思いましたか。
変わっているなあって思っていました。最初は慣れなかったです。でも今は(入学時よりは)眠りに入るまでの時間が短くなりました。
10分間で寝られたなあって実感は得られますか?
ちょっとは得られます。でも、できればもうちょっと時間が欲しいなあって。
寝た後はすぐに目覚められるものですか?
わりとすぐに。時間が少しなので眠りに深入りしないです。
「ウトウトタイム」があるのとないのでは集中力に違いを感じますか?
テスト前とか、授業のとき集中力が絶対に変わるなあって感じます。平日は塾があるので0時くらいに寝ています。どちらかというと睡眠時間が短い方だと思うのでウトウトタイムがあってありがたいです。
「今はシャキッ!と集中できているなあと自覚」

「ウトウトタイム」があることで何か変化がありましたか?
小学校の頃はお昼ご飯を食べた後、5時間目に眠くなってしまっていたんですが、「ウトウトタイム」で眠ることによって今はシャキッ!と集中できているなあと自覚しています。
「ウトウトタイム」の後に、眠くなることはないですか?
「ウトウトタイム」の後は掃除なのですが、掃除中にテンポが速くて明るめの曲が流れるのでその時に体を動かすことで目覚めます。
夜は何時くらいに寝ていますか?
大体22時半くらいです。7時間くらいは寝ているけど「ウトウトタイム」があることで午後の授業でもスッキリと集中して受けられるようになりました。
「10分間でも寝たら集中の度合いが変わってきます」
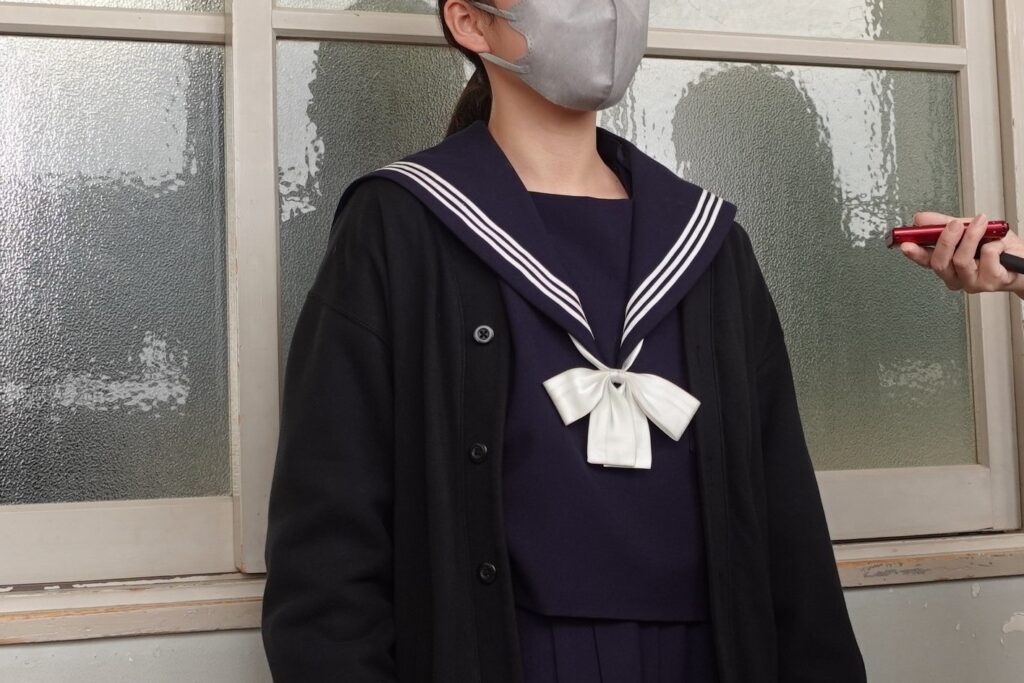
「ウトウトタイム」についてどう思いますか?
みんな午後の授業中に寝ることが少なくなったので、良い仕組みだなって思います。最初の方はぐっすり寝すぎてかえって授業中に眠くなってしまってきつかったのですが、慣れていくと、この仕組みがいいのかもって気づけました。
習慣になっていくとできるものですか?
はい。慣れですね、やっぱり。最初はきついのですが、10分間で眠れるようになって、寝た後はサッパリしたー!ってなります。10分間でも寝たら集中の度合いが変わってきます。夜の睡眠に影響もなく、よく眠れます。
「ウトウトタイム」の時に教室がうるさくなることはありますか?
先生がいない時にクラスに1人くらいは・・・ですが、学級委員が早く寝てって声をかけたり先生が見にきたりするのでうるさくなることはあまりないです。
「ウトウトタイム」を実施する意味について、生徒のみなさんは理解していますか?
宇土高校の先輩たちが睡眠の研究をしていて、その研究発表を聞いているのでウトウトタイムの意味や大事なことだというのはみんな理解しています。
効果的な午睡の取り方を研究中の「睡眠研究班」
「ウトウトタイム」導入をきっかけに生まれたのが課題研究「睡眠研究班」です。所属する宇土高校の生徒たちが、睡眠と記憶、午睡と集中力、午睡とストレスの関係など、睡眠をテーマにした様々な研究に取り組んでいます。
過去には「睡眠の質に影響を与えないカフェインの摂取方法」を探った高校3年生の研究が、日本霊長類学会大会の最優秀中高生発表を受賞。また日常に手軽な運動を取り入れることで睡眠の質を改善できないかと、自転車を活用した「サイクリングが睡眠に与える影響」といったユニークな研究も行われています。
そんな「睡眠研究班」のみなさんにもインタビューしました。

Aさん 「小学校の頃はぶっちゃけ午後の授業が眠たすぎて寝てました。ウトウトタイムで寝るようになって午後の授業でも眠くなくなりました。」
Bさん「ウトウトタイムで眠ることで瞼が軽くなります。」
Cさん「登下校で自転車を使うからウトウトタイムがなかったら白目で自転車漕いでたかも。」
Aさん「休日でもウトウトタイムを取り入れています。家で寝ていると“ウトウトしすぎ”なんて言われたりもします。」
このように「ウトウトタイム」に肯定的な意見がある一方で、こんな声もありました。
Bさん「寝るともっと眠くなってしまいます。」
Aさん「中学1年生の頃はウトウトタイムが15分間ありました。でも今は10分間に短縮されています。」
Cさん「中途半端なところで起こされてしまって、よけい眠くなってしまうのです。そこでもっとウトウトタイムが長い方がいいのではないかと研究を始めました。」
そこで、夏休み中に予備実験を実施。
脳波を測る器具をつけて寝て、どのくらいで眠りに落ちているか、どのくらいで自然に目が覚めているか等を計測しました。
その結果、入眠までには5~10分かかることが分かり、10分間の「ウトウトタイム」では時間が短すぎて十分な睡眠がとれていないのではないか、ということが見えてきました。
今は、「ウトウトタイム」を伸ばしても夜の睡眠に影響がないことを実証して学校側に提示できるよう実験を進めており、またこれらの研究成果を学校や学会で発表する予定だそうです。
ウトウトタイムの導入経緯と成果とは?

後藤裕市指導教諭に導入の経緯などお話をうかがってきました。
「ウトウトタイム」というネーミングがいいですね。
当初「お昼寝タイム」などの案もありましたが、ここはやはり「宇土」は譲れないと、「ウトウトタイム」に決めました。
「ウトウトタイム」をはじめたきっかけを教えてください。
大きく2つの要因があげられます。1つ目は、かねてから5時間目の授業に眠気を訴える生徒が多く課題感があったこと。2つ目は、当校が2013年文科省からスーパーサイエンスハイスクールに指定されたこと。これらをきっかけに筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構(IIIS)の柳沢正史教授と連携し、中高生の勉強・部活動のパフォーマンスを向上させる取り組みをはじめました。
当時、当校では朝の課外授業が7時半からあり高校3年生になると夕方にも課外授業を実施、合計1日10時間も授業時間がありました。課外授業の他にも、塾通いや部活など、生徒たちは多忙です。こうしたことを踏まえ、2014年に中学、高校で全校生徒を対象に生活習慣に関するアンケートを実施したところ、夜の睡眠時間は7時間未満という生徒が全体の約8割という結果でした。さらに、睡眠時間が7時間未満の生徒の約9割は学校で眠気を感じており、6割弱の生徒が5限目に眠気を感じているということがわかり、「ウトウトタイム」導入の後押しとなりました。
スタートにあたり周囲からの声はいかがでしたか?
当初は職員の間でも午睡をとることへの効果に半信半疑でしたが、はじめてみたら「意外といいかもね」という空気感に変わっていきました。保護者からも「仕事をしていて昼食後に眠くなる」というご自身の経験もあって理解が得られました。
生徒みなさんへ向けてアンケートも実施されていますが、データが裏付けとなりましたか?
はい。2014年にウトウトタイム試行後に生徒たちにアンケートをとったのですが、午睡の効果・授業の集中力を実感し、午睡の導入に肯定的な生徒が80%を超えたのです。まずは「おもしろい取り組みだね」という周囲の声からはじまりましたが、予備調査や事後調査の結果を柳沢教授に見ていただき積極的休養の重要さについてをアドバイスいただいたことも大きいです。
「ウトウトタイム」を設けてからどのような変化がありましたか?
まずは午後の授業での居眠りが大幅に減少しました。午後の授業において集中力や意欲が向上したり、夜の睡眠の質が向上した、といった効果も得られたようです。
10分間ですぐに眠れるものですか?
最初のころは慣れない生徒もいました。慣れてくるとウトウトタイムの音楽が流れると眠くなる、という条件反射のようになっているようです。午睡スタート時点では音楽の音を大きめにして、だんだんと音量を小さくしていくような仕組みにしています。

長く続く取り組みですが、導入から定着までは、どのような道のりでしたか?
導入から10年が経ちますが、大きなスパンで見たときに3段階に分けられると思います。
初期のころは試行錯誤の連続でした。午睡した生徒に関しては「効果があった」「午後の授業で集中できるようになった」とポジティブな回答や保健室の利用者数が減ったという変化があった一方、「教室で(落ち着いて)眠れなかった」など、眠りたいけれど環境が要因で眠れないという声や、そもそも眠くない生徒もいました。そこから、消灯する、カーテンを閉じる、音楽を流すなど、眠る環境づくりの工夫をはじめました。はじめはオペラを流してみたのですが、これは1日でやめました。歌詞があると眠りに入りづらいようです。
中期では生徒たち自身が「ウトウトタイム」の効果を検証し、睡眠とのより良い向き合い方を研究しようという動きが出てきました。「睡眠と運動の関係」「昼寝と作業効率の関係」など生徒主体の学びとなり、探究活動へと広がっていきました。
現在では、生徒たちが睡眠自体への興味や関心を持ち、より理解を深めるために、毎年、柳沢教授の研究室にうかがったりするなど校内にとどまらない活動になっています。
取り組みが継続している要因は何でしょうか?
学校内の一教員だけで推進していくと変えられないこともあったかもしれないですが、「スーパーサイエンスハイスクール」に指定され、それにより学術的なサポートが得られたなど好条件が重なったこと、周囲の理解と協力、そして何より生徒たち自身が主体的に研究しようという土壌が根付いたことかもしれません。また「ウトウトタイム」の時間だけが学校の中で独立してあるのではなく、定期的に睡眠に関する講演会を行ったり生徒たちが研究発表をするなど様々な教育活動をつなげることを心がけてきました。
最後に、「ウトウトタイム」の効果について、後藤先生はどうお考えでしょうか。
「ウトウトタイム」を導入したことにより成績が向上した、など直接的なことは言えませんが「ウトウトタイム」を続けていく中で、睡眠の重要性を認知してもらう、という睡眠教育につながっていきました。最初は午後の授業の眠気対策といった課題解決の視点からスタートしましたが、徐々に睡眠がもたらす効果や生活リズムを整えることの大切さなど、生徒たちがもっと幅広い視点で睡眠を考えるようになっていると思います。
お昼寝時間がある学校ってどんな学校なんだろう?というまずは単純な興味から熊本県立宇土中学校・高等学校に取材をお願いしました。大人でも、仕事中や昼食後など、瞼が重くなる瞬間は多々あるので、学校でお昼寝時間が設けられていることに、羨ましささえ感じます。午睡が成績アップにつながっているかは不明とのことでしたが、結果として子どもたち自身が自分の生活リズムの見直し、睡眠を大切にする意識につながったという点が何よりの成果だと感じられました。