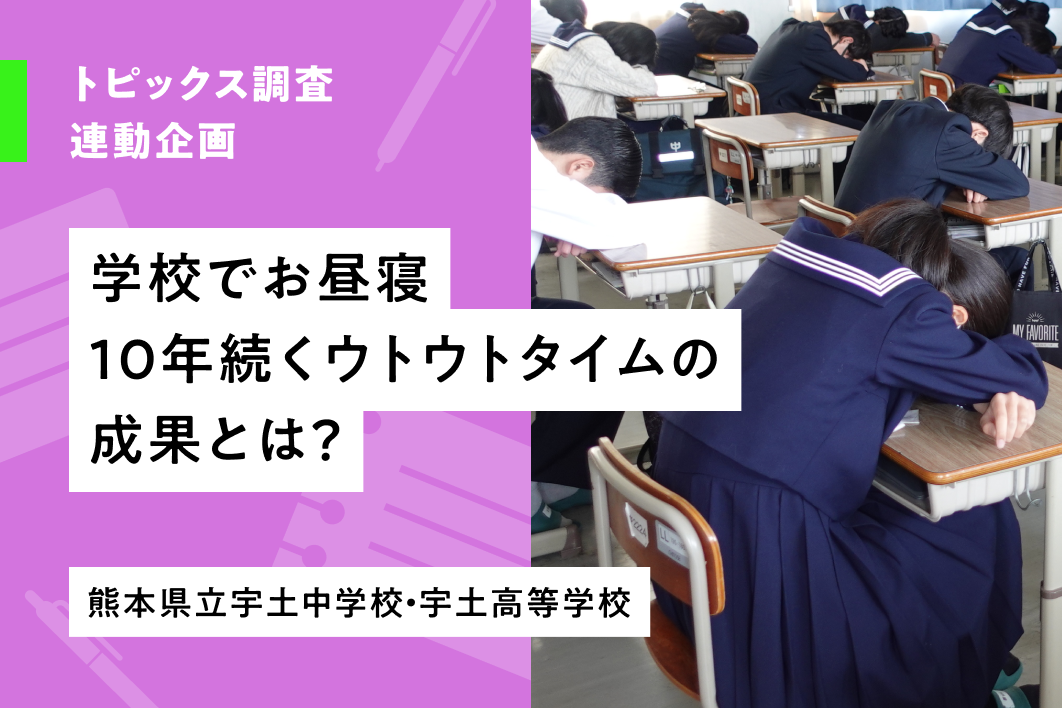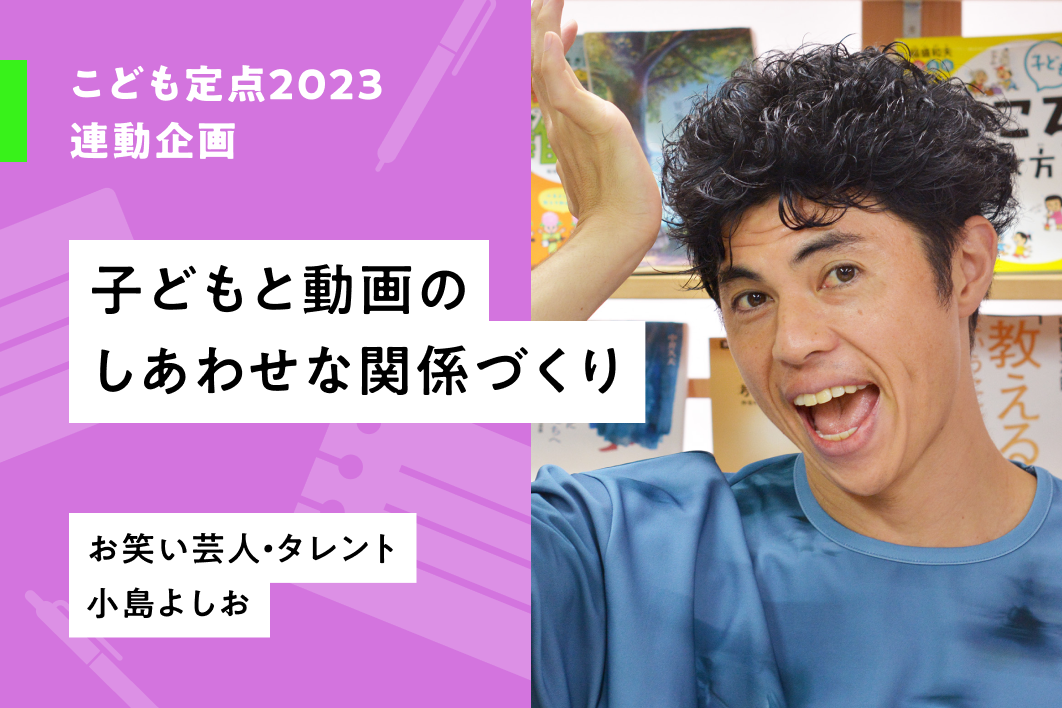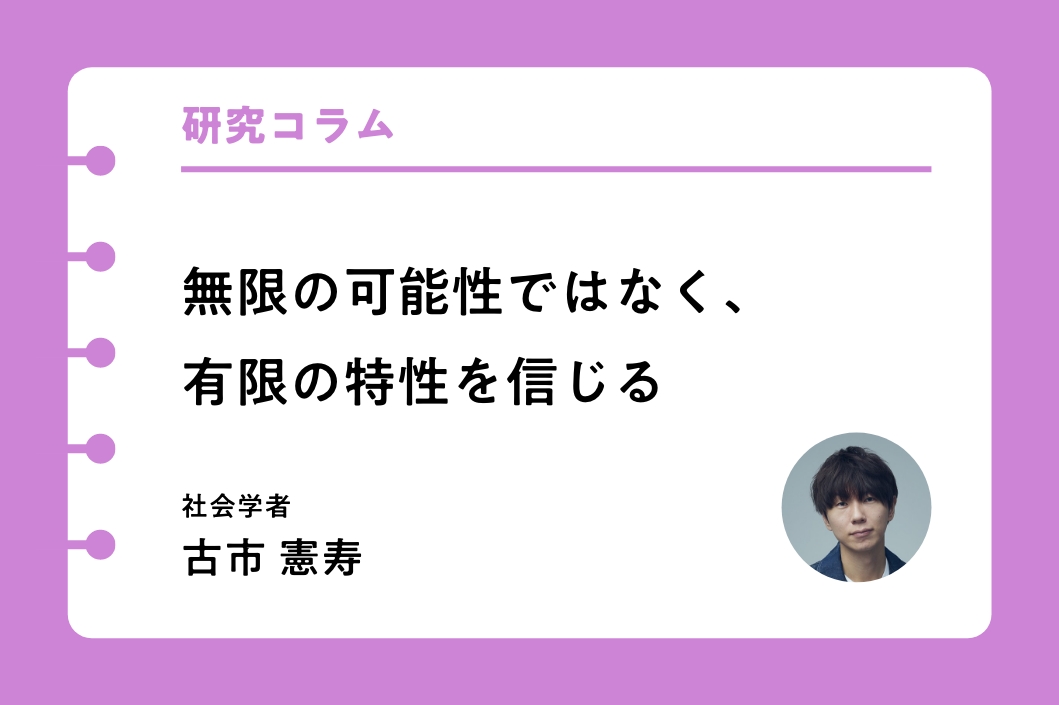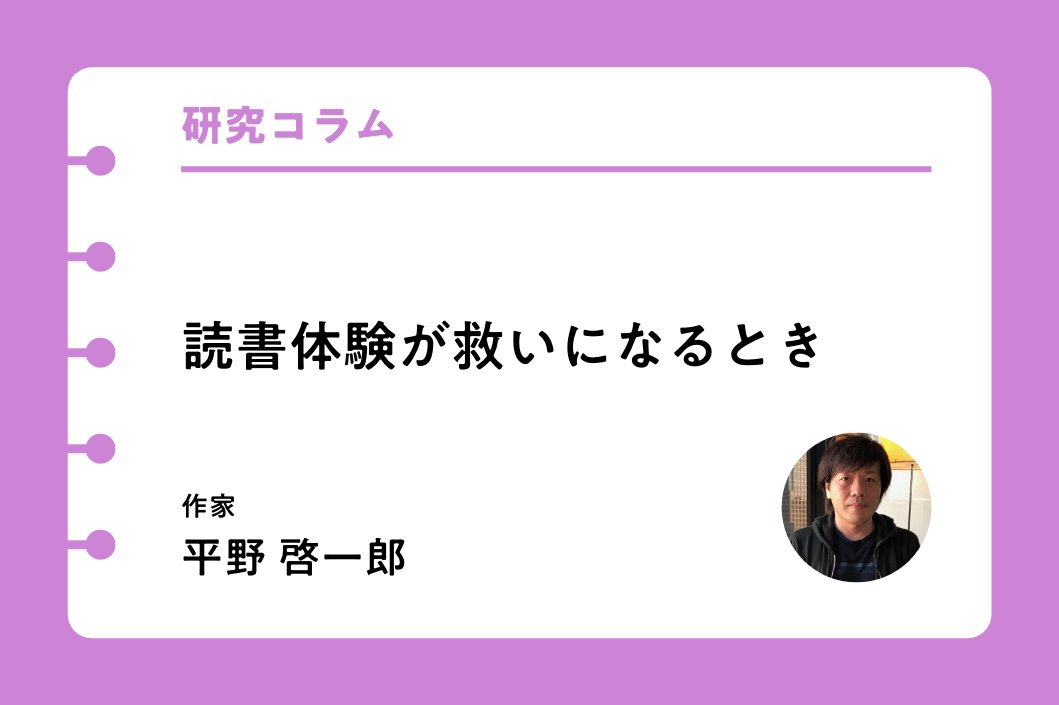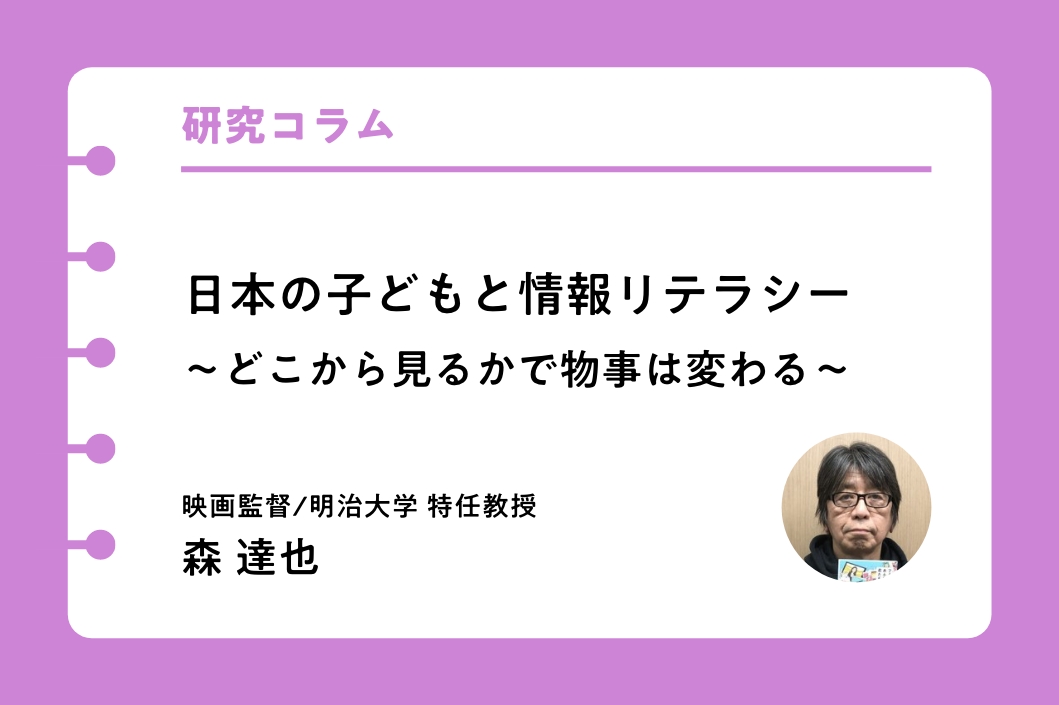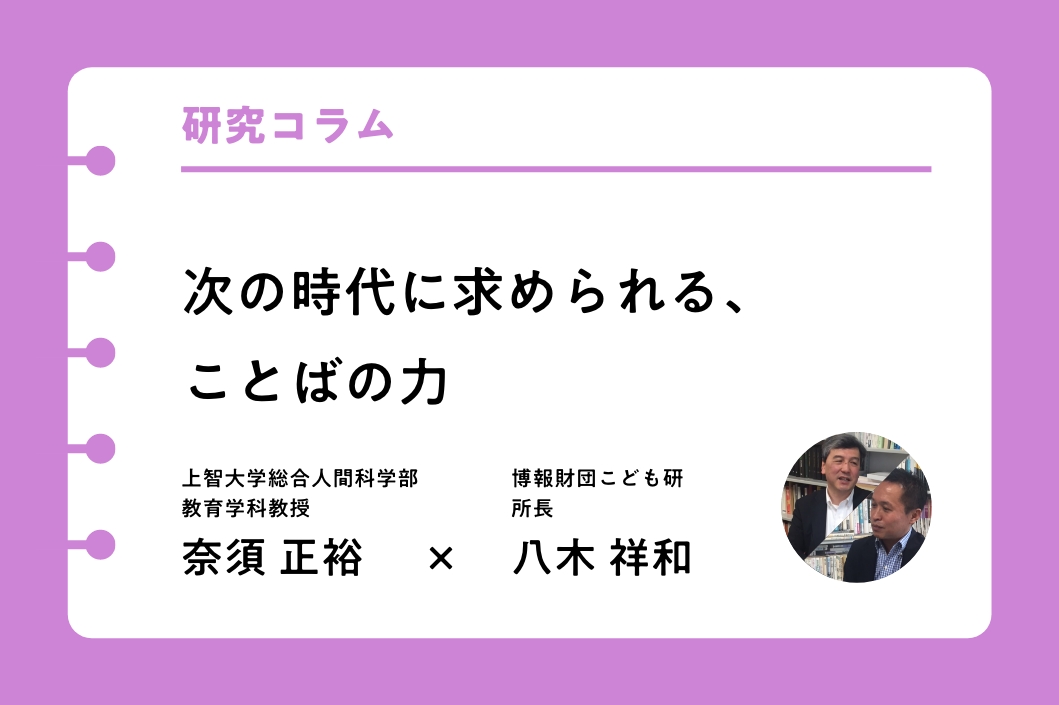人類の進化200万年をさかのぼり、
心の発達を科学する
京都大学・明和政子教授(比較認知発達科学)に聞く

人間は言葉を持つ動物であり、複雑な心を持つ動物でもある。 では、人間の心とは何なのだろうか? 社会の変化や情報技術の急速な進歩によって、子どもたちの心はどんな影響を受けているのか? このような本質的な問題に、比較認知発達科学という学問領域からアプローチしようとしている京都大学・明和政子教授にお話を伺った。
生物としてのヒトを考える
ご著書『ヒトの発達の謎を解く―胎児期から人類の未来まで』(ちくま新書)の中でとても印象的だったのが、人間の脳神経ネットワークの発達の部分でした。人間の場合、生まれてから長い時間をかけて脳神経系を変化させていきます。生後急速に密度を高めていくシナプスの結合は、例えば視覚野や聴覚野など比較的早くに成熟する脳部位だと、乳児期にピークとなり、その後、生まれ落ちた環境から得る情報処理に不要なシナプスは刈り込まれていきます。刈り込みが落ち着く、つまり、完成するのは7,8歳です。他方、もっとも複雑なことを考えたり、イメージしたりすることを担う前頭前野だと、刈り込みが終わるのは25歳以降です。脳の構造はどんどん複雑になるのではなくてシンプルになっていくというのが意外でした。

ため息が出るくらい美しいんですよね、生命現象って。 つまり、部品を沢山持って生まれてくるけれど、生まれ落ちた環境次第でよく使うものだけが生き残っていく。自然淘汰が脳の中でも起こっているということです。
私は生物学者として、「ティンバーゲンの4つの問い」(注1)という生物の原理を知ることでしか、生物の本当の姿は見えてこないと考えています。ティンバーゲン(生物学者・1908~88)は、生物の機能や行動を理解するためには「4つの問い」すべてに答える必要があるとしました。でも、今の科学研究の多くは、このうちの直接的な要因である【至近要因】のみを掘り下げる方向に偏っていると思うのです。ヒトの未来のあり方や次世代の育ちについて考えるためには、生物としてのヒトの本質そのものを理解する必要がある。これだけ急激な環境変化が起きているときにこそ、人類の進化のプロセスまでさかのぼって、今起きている、あるいは今後起こりうる問題の背景、理由を考えなければいけない。それが私のスタンスです。
*注1「ティンバーゲンの4つの問い」
1973年にノーベル生理学・医学賞を受賞したオランダの生物学者、ニコ・ティンバーゲン(1908~88)が提唱した理論。生物のふるまいを理解するためには、以下の「4つのなぜ」すべてに答える必要があると指摘した。
① 至近要因
ある生物の行動が引き起こされている直接の要因は何か?
例)ヒトの脳内には、言葉の理解と表出を可能にするどのような構造、機構が存在するのか?
② 究極要因
その行動はどのような機能をもって進化してきたのだろうか?
例)ヒトの言語能力は、どのようなメリットがあって進化してきたのか?
③ 発達要因
その行動は、その生物の一生の過程で、どのような発達をたどって獲得されるのだろうか?
例)ヒトの乳児はいつ頃からヒト特有の言語を特徴づける文法の萌芽を発するようになるのか?
④ 系統進化要因
その行動は、その生物の進化の過程で、どの祖先型からどのような過程をたどって獲得されとのだろうか?
例) 現生人類のヒト属(Homo)が、私たちと同じレベルの言語を獲得し始めたのはいつ頃か?
出典:『ヒトの発達の謎を解く―胎児期から人類の未来まで』
身体体験を通して言葉は獲得される
私たちはオノマトペをよく使いますよね。オノマトペは,赤ちゃんが言葉を獲得していくうえで重要な役割を果たします.「ボール」という言葉がまだ言えない赤ちゃんは「コロコロ」と言いながらボールを転がす。かなづちを操作して「トントン」と言いながら、最終的に「カナヅチ」という言葉を覚えていくのです。こうした身体での体験が、乳児期にはとりわけ重要です。身体体験というプロセスを基盤として「名詞」を獲得していくのです。AIに「カナヅチ」「ネコ」「クルマ」と教えるのは簡単です。カナヅチの画像と音声をマッチングさせることはすごく簡単にできるのだけれども、「トントン」から「カナヅチ」への推論というのは身体が無いと無理。特に動詞はそうですね。
AIにとって名詞の獲得は簡単ですし、文法の規則性をある程度学ぶのも上手。でも、(熱いモノを触って)「熱いっ!」ということから、「心が熱い」といった比喩をイメージすることはできません。だから、AIが言語を学習することと、人間が身体経験を通して言語やシンボルを獲得していくプロセスは全く違う。学習と発達はまったく異なるのです。
自分の巣を守るためにオキシトシンが分泌される
日本の場合、明治維新以降の近代化で標準語が導入され、義務教育では体操や音楽の授業で身体や感覚の統制がはかられたと思うんです。土地の持つ風土から生まれた身体性の濃い言語である方言が失われていった影響について、生物学の観点から何か言えることがあるのでしょうか。
生物の体の中では「自分の巣を守る」というシステムが起動します。例えばオキシトシンという物質は子孫を残すために哺乳類動物が特に進化させてきたホルモンです。それがどういう働きをするかというと、子どもや家族等よく知っている個体と身体接触をすると、その対象に対して非常に親和的で優しい情愛を湧き立たせるのです。面白いことに、オキシトシンは見知らぬ個体に対しては攻撃性を高めます。子育て中のラットの巣に見知らぬラットを入れると、親は激しくその個体を攻撃します。
オキシトシンは心地よくさせるホルモンというイメージだったのですが、攻撃性にも関わっているのですね。
つまり、身内に対しては非常に信頼して暖かい気持ちというbonding(絆づくり)を強くするとともに、外側の集団にはむしろ攻撃的になるという巧妙な生体システムが備わっているのです。このシステムは、人間の村社会にもあてはまるでしょうね。村が存続するために、外部を排除せざるをえない長い歴史があった。外集団と内集団の境界がはっきりしていた。しかし、近代化によって外集団と内集団の区別があいまいな社会構造になってきた。自分が所属する集団とそうでない集団の境界がはっきりしなくなったので、子育てを安心して行える空間がみえづらくなった。信頼できる誰かがそばにいる、ということがなくなり、いわゆる「ワンオペ」、母親による孤立育児が増え続けているのだと思います。
マネをすることで仲間意識が生まれる
最近の若者の間で盆踊りが復活してきているという話も聞きますが、それもオキシトシンの放出と関わっている、近代社会への反動的な現象なのかもしれませんね。
「カメレオン効果」と呼ばれる現象があります。ヒトは誰かから真似される、同じ動作を共有すると、その相手のことを信頼したり、親和的な感情を抱くのです。ダンスも同じです。一緒に踊っていると仲間意識が生まれる。
同じ動作をすると,なぜ親近感が生まれるのでしょうか?
生存上、意味があったからでしょう。「ミラーニューロン」という神経細胞群がそれに関与していると考えています。子どもたちは言葉を話す前から、周囲の大人たちの言葉や動作をサル真似します。真似することによって、遺伝的に伝わらない知識や技術を非常に効率よく学ぶことができます。サル真似は、じつはヒトに特異的に備わっている能力で、サルもチンパンジーもラットもサル真似はできないのです。サル真似は、ヒトの祖先がチンパンジーの祖先と枝分かれした後のどこかの時点で獲得してきた形質だと考えられます。真似することは、学習の効率性に関わるだけではありません。相手のことを真似ると「あなたの心がまるで私のもののように」感じていきますね。いわゆる、他人の痛みがわかる、ということです。日本人であれば、相手が梅干しを食べているのを目撃したら、自分も自然と唾液があふれてくるでしょう。しかし、私が住んでいたアフリカの子どもたちの前で梅干しを食べても、彼らには何の反応も起こりません。彼らは梅干しを食べた経験がないからです。同じ行動を共有するという身体経験によって、思わずその相手に感情移入する。これが内集団において信頼を強める根幹であり、その人が安全な人かどうかの判断基準になるわけです。内集団で催事、お祭りなどがなぜ多く行われてきたか、これでお分かりでしょう。

共通体験を失った社会はどうなるか?
そうすると社会学の分野で言われている「グローバリゼーションによる個の断片化」で、共通体験が失われていくことの影響は大きいですよね。共通の体験があったとしてもネットでのヴァーチャル体験が中心になっていくとすると、そこでは身体を他者と共有する経験がはく奪されるから、オキシトシンが出にくくなっていくのかもしれないですね。
その科学的検証はこれからです。ここで指摘しておきたいのは,私たちの世代は、脳が発達する時期に色々な大人と身体を介して関わるというリアルな体験をして育ってきていることです。私たちの脳は、こうした経験を得てすでに完成している。しかし、これから生まれてくる子どもたちは、ヴァーチャルとリアルが融合するという未曾有の環境の中で育つことになる。誰かと身体接触する、身体経験を共有するという日常は希薄になっていくでしょう。子どもたちの脳は未成熟です。こうした新たな環境は、子どもたちの脳の発達、たとえば,先述のシナプス刈り込みなどにも大きな影響が出てくるはずです。これまでの環境とはまったく異なる情報処理が行われるようになるわけですから。体性感覚野は特に変わってきていると思います。この仮説はあと数十年後には検証されるでしょう。テクノロジーは指数関数的に発達していますから、さらに予測不能な事態が次世代の人間の脳に起こるかもしれません。
新しい人類の誕生?それとも?
今までの人間の順序でいくと、まず身体性のあるリアルな体験があってからメディアでの体験をしたわけですが、その順序が逆になってしまうと、アタッチメントやぬくもりがあることが嫌になってしまうことがあるのではないでしょうか?
他個体と身体経験を共有することでオキシトシンを高め、社会関係を築いていく。こうした生体システムをもった人類は、今後新たな環境に適応できなくなって滅びていく。身体に対する感受性がさほど強くない個体だけが生き延びるということもあり得るかもしれません。ただ、人間の身体とその生体システムは何百万年という時間をかけて獲得されてきたものですから、この20~30年でそう簡単に変わることはないと思います。しかし、環境と生体システムのミスマッチは今後いっそう大きくなっていくはすですから、精神疾患を発症するリスクはどんどん大きくなっていくと思います。
長い時間をかけてつくられてきた人間の体ですが、その人間の体が適応できないような環境を人間自身がつくってしまったということになりますね。そんな環境変化に対抗しようという揺り戻しが人間自体から起きてくることはあるのでしょうか?
まさに、そこのところで私は基礎研究者としての役割を果たしたいのです。生物にとって身体性、環境と身体の相互作用がいかに重要かを理解してもらうために、本を書いたり講演活動を行っています。とくに、脳が未成熟な子どもたちと接しておられる現場の方への啓蒙に力を入れています。スマホを見ながら赤ちゃんに授乳していると、脳の感受性が一番高いときの絶好の機会を逃すことになりますよと。母親と見つめ合いながら身体接触をすることで、人間にとって大事な生体システムができあがっていくのですよ、と。
社会で子どもを育てる
母親の子育て環境が厳しくなっているわけですが、もともと人間は共同養育をやってきた動物でもあるわけですよね。社会全体で子どもを育てるような動機づけをしていくということはないのでしょうか?
まさしく、それを目指していかないといけません。村社会が無くなった今、「現代版」の共同養育システムが作れないか、と。問題は、今の社会は、オキシトシンが出やすいような内集団をつくりにくくなっていることなんです。例えば、男女共同参画社会という方針が出されても、その実現はかんたんではありません。現代の親たちは、内集団の子どもに関わったりする幼少期からの経験がないので、育児に適した脳のはたらきが形成されていないのです。子育てを終えた中高年の女性が、バスや電車のなかで赤ちゃんに声をかけたり、あやしたりするようすをよく見かけますが、これは、その女性たちは子育て経験をへて、育児に適した脳を形成してきたからです。ミラーニューロンもそのひとつ。子どもを見ると、過去の経験から自然とオキシトシンが沸き立つのですが、子育て経験のない者はそうはならない。とくに、長年会社という社会が生活の中心であった男性にとっては、子どもの泣き声は、騒音として感じられるでしょう。喫緊の課題として、私は、母子手帳の改変を行う努力をしています。子どもに触れたことのない世代は、女性も男性もですが、親としての脳や心を発達させるための準備をすることが必要です。そうした情報を、きちんと母子手帳に盛り込む。「父親は、母親の心を支えましょう」のレベルではなく、母親とともに育てるという、育児に積極的に参加することの必要性を科学的根拠をもって訴えていかねばなりません。
そういう意味では、子どもの頃から年下の子の面倒をみる体験をするのは良いことですね。集団登校も良い仕組みかもしれません。
ああいうのはいいんですよ。今は少子化ですし。中学生の保育園体験というのがあるんですけど、すごく大事ですよ。昔は当たり前にあった経験を、今は「特別に」提供しなければいけないという時代なんでしょうね。幼少期のうちに、誰かとコミュニケーションすることに喜びを感じる経験をもち、そうした予測が可能となる脳を育む。誰かとコミュニケーションすることでオキシトシンが高まる心地よい身体接触体験を豊かに提供する。この根っこの部分を大切にしなければならない。それがはく奪される(虐待経験など)と、思春期にうつなどの精神疾患を発症するリスクが大きく高まることがわかっています。
幼少期のアタッチメントが、人への信頼を生む
対人関係上の脳の予測性というお話がありましたが、やはりアタッチメントによって予測性が高まるということなのでしょうか?
アタッチメントという言葉を科学的に説明したのが「予測性」という概念なんです。対人関係の予測性、つまり、この人は大丈夫、安心」という予測を脳内に形成することがアタッチメントなんです。
そうすると予測のためには、個体を識別する情報量は多ければ多いほど良いということになるのでしょうか。メディアが発達すると、どうしても情報が削られてしまうような気がするのですが。
現在のデジタル社会は、視覚情報や聴覚情報などの外受容感覚(注2)にすごく偏った情報処理を行う環境を作り出しています。他者との身体接触によって身体に心地よさを沸き立たせる内受容感覚の経験は、どんどんはく奪されている。そうした環境の中で育つことになる子どもたちの脳や心には、いったい何が起こるでしょうか。視覚、聴覚を中心とした外側からの刺激は豊かにあるけれど、身体接触によって起こる心地よさが結びつくような経験は十分提供できているでしょうか。こうしたことを脳が顕著に発達する幼少期に十分経験しておくことが、人間という生物として生存するためには不可欠です。 その点において、最近増えている子ども食堂はとても良い施策ですよね。みんなと一緒に食事をし、目をみて、笑い合う。こうした時空間では、外受容感覚とともに、内受容感覚からくる心地よさが統合経験される。他者と身体経験を共有する経験を豊かに提供して、他者とのコミュニケーションのなかで身体内部の心地よさを感じさせることが、発達支援にとって一番有効なんです。
*注2)外受容感覚・内受容感覚
子育てに関して「アタッチメント」という言葉がよく使われるようになってきている。イギリスの精神医学者ジョン・ボウルビィ(1907~90)によると、アタッチメントとは生物が進化的に獲得してきた生存戦略の一つ。アタッチメントの基本は発達初期にある特別な存在(特定の養育者)と身体をくっつけ、自分では制御できない身体の生理的変動や情動一定の状態に調整すること。
そして、これまでのアタッチメントの捉え方を超えて、養育者と乳児の身体を介した相互作用こそがヒト特有の社会認知の基盤であるという説に最近注目が集まっている。他者と分離して自己という意識を持つことはヒト特有の社会的認知の要だが、そうした認知能力を獲得する基盤となっているのは、身体レベルで自己とそれ以外を区別するという基本的感覚で、これを「身体感覚」と呼び、これは環境と動的に相互作用する過程で生じる。
身体感覚のうち「内受容感覚」は身体内部に生じる感覚で、「外受容感覚」とはいわゆる五感のこと。この外受容感覚からの情報と内受容感覚に由来する情報が統合される過程が非常に重要である。なぜなら、この統合こそが、ヒトだけが持つ心のはたらきである「感情の主観的な気づき」に深く関わっていると見られるからである。
(『ヒトの発達の謎を解く』より)
明和 政子
京都大学教育学部卒。同大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。京都大学霊長類研究所研究員、京都大学大学院教育学研究科准教授を経て、現在、同大学院教授。専門は比較認知発達科学。主な著書に『まねが育むヒトの心』(岩波ジュニア新書)『なぜ「まね」をするのか』(河出書房新社)『心が芽ばえるとき――コミュニケーションの誕生と進化』(NTT出版)『ヒトの発達の謎を解く』(ちくま新書)などがある。
明和政子研究室:http://myowa.educ.kyoto-u.ac.jp/