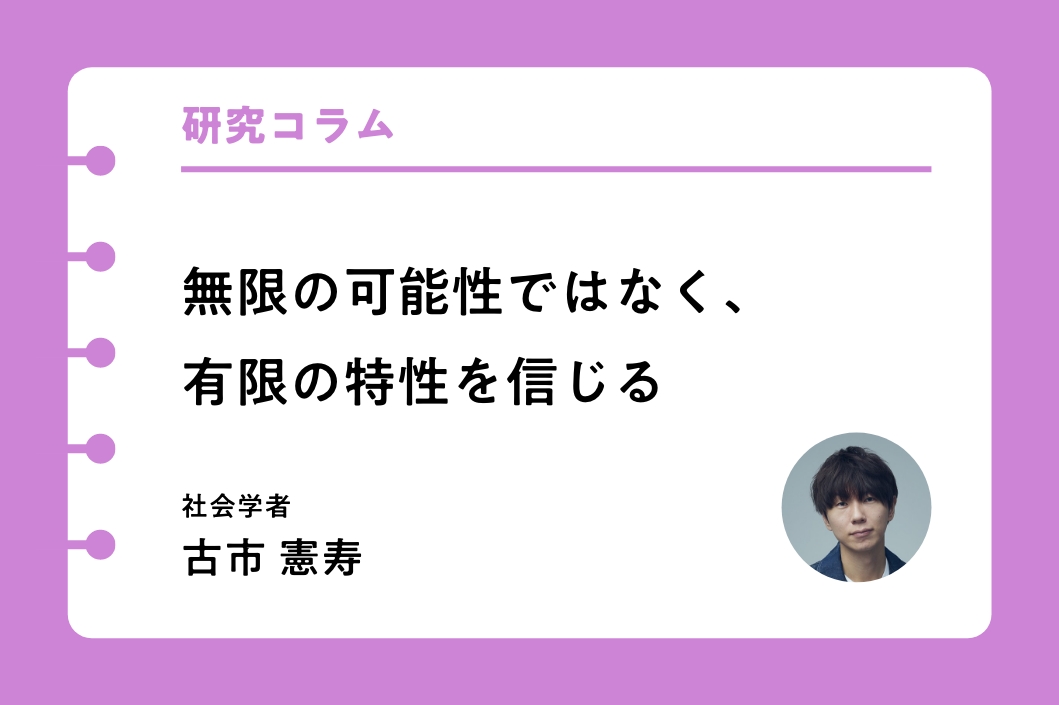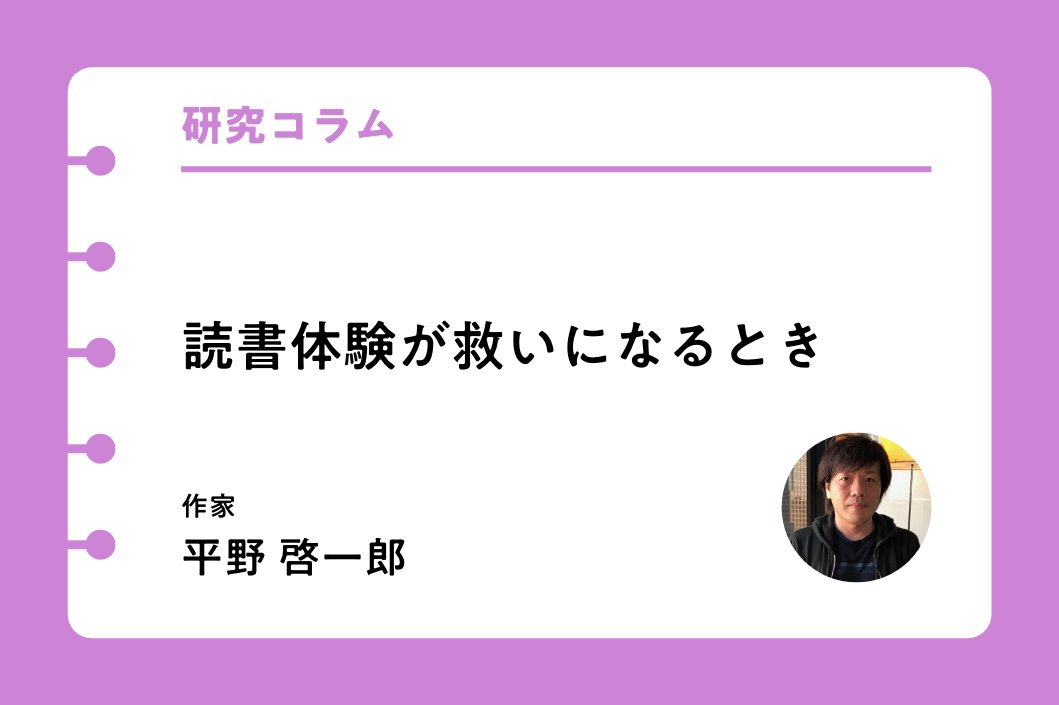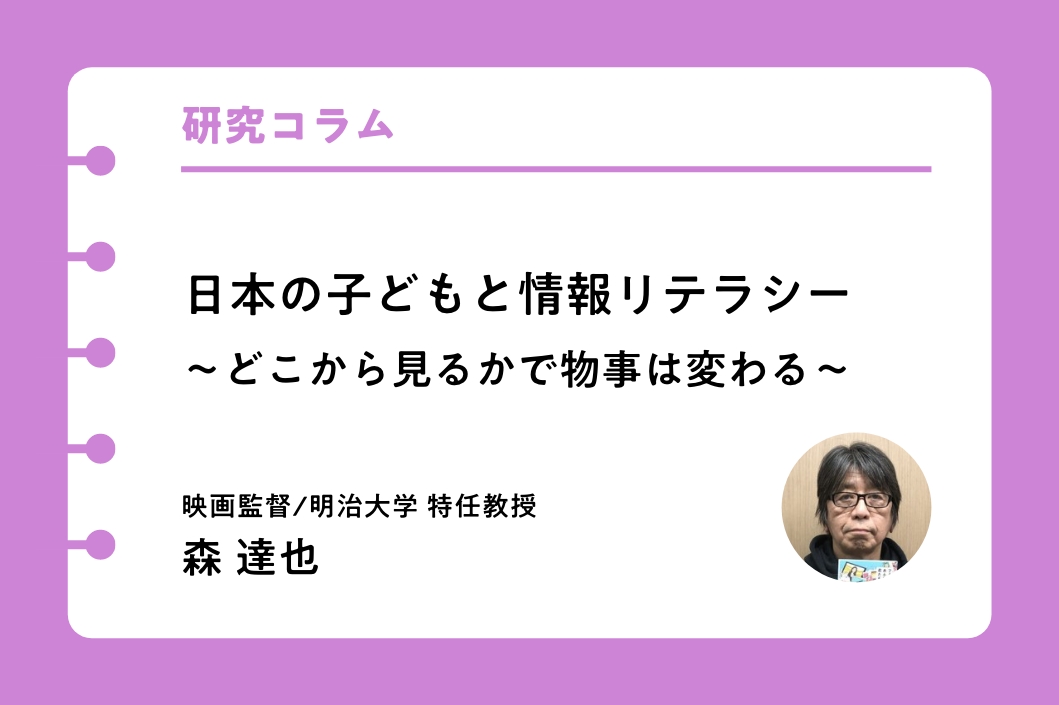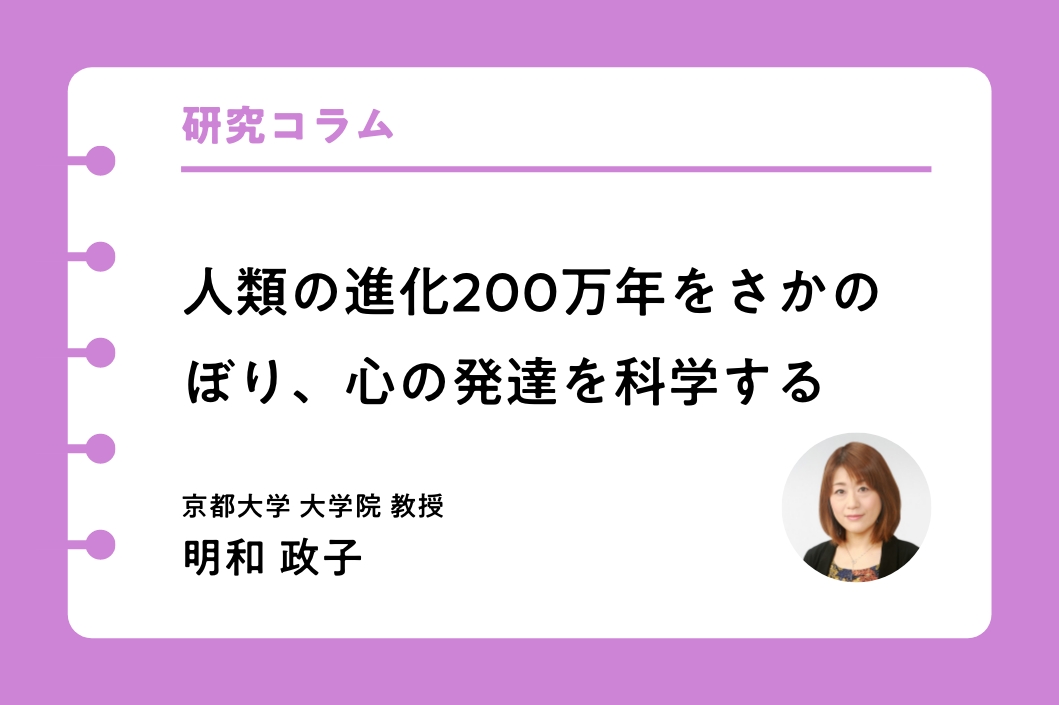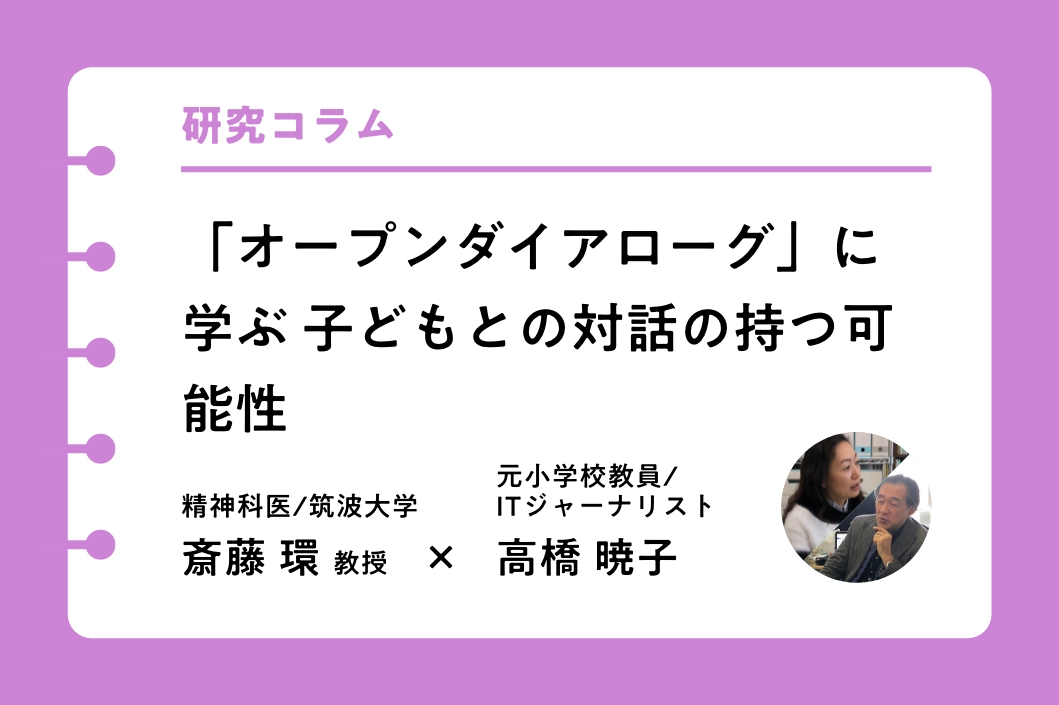次の時代に求められる、ことばの力
奈須正裕(上智大学総合人間科学部教育学科教授)
八木祥和(博報財団こども研 所長)

子どもの読解能力が低下していることが近年大きな問題になりつつあります。 改めて今、言葉を扱う能力をどのように養っていくべきなのかが問われているのではないでしょうか。 今回は、教育界のキーマンである上智大学・奈須正裕教授に、「ことばの力」をテーマにお話しを伺いました。
「書く」ことが苦手な日本人
八木今回は当研究所の諮問委員も務めていただいている、教育界のキーマン、上智大学の奈須教授にお話を伺います。当研究所は「こども」「ことば」「教育」に関連する調査研究を行っておりますが、先生は次の時代に求められる「ことば」の力、「ことば」の教育についてどのようにお考えですか?
奈須「ことば」の教育、ということでは、「読む」「書く」「話す」がありますが、一番課題が多いのは、いわゆる「書く」こと、言い換えれば、文章の生成だと思います。
多くの人にとっての「母語の教育」、いわゆる「国語」の教育をやるときには、母語を学習言語のレベルまで引き上げていくことが必要となります。学習言語というのは、その言語を思考の道具にするとか、それを思想の表現のツールにするというレベルでの言語のことをいいます。このレベルでの言語は、いろいろな教科を勉強する時の道具にもなりますし、抽象的・論理的に考えられる、とか、それを的確に表現できるとか、すべての学びの基礎になります。その中でも、「読む」ことに比べて「書く」ことは当然難しい。だから、ある意味では文章を生成する、「作文」する、というのが、言語教育の中心にあるべきだと思います。なお、「話す」ことばである「音声言語」も大事ですが、「書く」ことばである「文字言語」の方がよりフォーマルで、学習言語としてきちんと教えなければなりません。日本のこどもが海外に行った時に、ことばをすぐに覚える、というのは、音声言語です。日常会話まではカバーできるが、いわゆる学習言語といわれるレベルまではカバーしにくい、という特徴があります。
それでは、日本語の文章生成、「書く」こと、いわゆる「作文」ですが、この分野には、どのような課題があるのでしょうか。日本の学生が海外に行った時に、日本の学生は論理性がない、論理的でない、とよく言われます。しかし、彼らの思考が論理的でないのかといえば実はそうではなくて、論理的に考えたことを表現する技法とか型を教わっていない、ということなのです。試しにある種の型、論理的に表現し、説得的に伝える型を教えた上で留学させると、絶対にそんなことは言われません。日本の学生は、小・中・高校でそういう練習をしていない、ただそれだけなんです。では、小学校、中学校が何をやっているかというと、「読書感想文」と「行事の作文」ですね。場合によっては、それが「作文」だと大人も思い込んでいる。ヨーロッパでもアメリカでも、そんなことはやっていません。
日本語教育の歴史は明治時代に日本の教育が始まった時までさかのぼります。当時「作文」は、完全に大人の文章を真似て、全くこどもに体験、経験のないことを書かせるものでした。明治時代は、それがとても多くて、絵も、いわゆる図工の領域も「臨画」といって模写でした。お手本を正確に模写する、それが明治期の教育。完全な暗記で、意味は重要ではなかったんです。それはさすがによくない、とわかったのは大正時代。第一次大戦後、いわゆる大正デモクラシーの時代に、日本は大正自由教育といって、こどもの心や発達段階を全く無視して、大人が教え込むことは、とても良くないと議論された時代だった。
作文の場合、「赤い鳥」という児童文学雑誌を中心に、いわゆる児童文学運動が起き、中心人物だった作家の鈴木三重吉は、こどもにとって、まったく経験も実感もない文書をただ模写させるというのはことばの教育としてはとてもおかしい、と課題提起しました。つまり、こどもはいろいろなことを考え、感じているから、こどもがリアルに経験したことを綴って、と同時にそれに対していろいろ考えていることや思いを書く、ということを中心にすべきであると訴えました。こどもに自由に書かせなさい、そこで発露するこどもらしい感情が大事だ、ということです。明治時代、徹底して型を教えていたのに対して、「型を教えない」「型が悪だ」という考え方です。民主主義が大事にされたこの時代に、こどもたちが共通して経験している感動や思いがあるのは行事です。運動会とか遠足とか、皆が経験している楽しい行事を足場に、みんなで書く。ただ、運動会や遠足の何をどんな風に書くのは自由でよいと。かけっこを書く子もいれば、お弁当を書く子もいていい。面白いのは、それを皆で並べてみた場合に、一つ共通の経験に対して個性的で多様な感じ方があり、表し方がある、ということじゃないか、となったわけです。それ自体は悪いことではありません。アメリカでも実は1930年代~40年代には、そういう考え方が出てきていて、世界的な潮流でした。
ちなみに、日本語の「読み」、いわゆる「読解力」ついては、1930-40年代に、科学技術立国をめざした中で、情緒豊かで楽しい物語を読ませると同時に、科学的で論理的な文章を読ませることもしました。だから、実は読解についてはよくできるんです。最大の問題は、読解でやっている構造的で論理的な文章を、「書く」機会は一切なく、読むことと書くことがシンメトリーになっていないということなんですね。

八木日本人がロジカルシンキングが苦手と言われるのは、教育において、「書く」よりも「読む」にバランスが偏っていたこと、論理的に「書く」ための型や技法を遠ざけてしまったことが影響しているのですね。確かに、私も社会に出てはじめてロジカルに書くことを求められた気がします。ほかの国ではどうでしょう?
奈須例えばアメリカの場合、ギリシャ・ローマ以来の修辞学(※1)に基づく型を教えていました。要は、伝統的な西洋における弁論・叙述の型ですね。特に、ベトナム戦争以降、アメリカでは高等教育が爆発的に拡大し大学進学率が一気に上がったのですが、その時に、論理的に考えられない、表現できないこどもたちが高等教育を希望してきて、それが非常に困るということになり、これがひとつの契機になって、1970年代~80年代にかけて初等中等教育でも、論理的に考えて表現するための作文教育をちゃんとやろう、という話になっていきます。その際、小学校でも、最初にまず結論を言って、そのあとに3つ位の根拠となる事例を示し、それを総括して、最初の結論をもっと強く説得力を持って語る―ファイブパラグラフという手法を教えるようになりました。最初のセンテンスがあって、それに対して3つの事例を出し、最後に結論(コンクルージョン)。これを小学校3年生くらいから教えています。各州の評価規準があって、小学校の学力として身につけるものとして、学習目標と規準が明確に設定され、指導を要請されています。
学習の達成度を明らかにすることを求められるのは、「エッセイライティング」です。学術研究とかビジネス、日常生活に対する有用性から考えられた技法で、論理的である、説得的であるということを大切にしながら、個人の解釈をちゃんと入れなければならない。事実をただ並べるだけでなく、その事実を自分はどう解釈して、何を強調してこの論理を形成するか、ということを徹底します。
もう一つの柱として、欧米にはエッセイライティングにならぶ「クリエイティブライティング」というのがあって、空想のオリジナルな物語を創作します。エッセイライティングという論理的な説明文と、クリエイティブライティングという物語づくりという二本立て。一方で、日本ではクリエイティブライティングは一切やらないですね。
なお、アメリカでは、「読解」については、原則多読です。たくさん読んでいるうちに自然に読めるようにする、というやり方です。たくさん読み、たくさん書くことの両輪で、論理の構造を理解する、そういう考え方に立っています。

八木「ことば」をめぐる日本の教育の変化について、もう少し詳しく教えていただけますか?
奈須今、学習評価をどうすべきかという議論が、小・中学校で広がっていますが、少なくとも中学校では、レポートをもっと評価対象にしてもいいのではないかという意見があります。こどもたちが自分の考えをまとめて整理して、ゆっくり時間かけて表現するレポートの方が、むしろ、その子の学力を的確に見ることになるのではないか、ということです。ただ、そういうと、面白いことに、多くの方が「レポートなんかにしたらみんな100点を取ってしまう」と反論します。つまり「レポート」は何か、理解していないんです。もっと言えば「レポート」とは、「何かをひき写してくること」だと思っている。逆に言うと「テストというのは何かを覚えるもの」としか思っていないわけです。そういうことが評価の議論で飛び出してしまうというあたりに、日本のことばの教育の問題があると思います。ある文章をもってくる、ある資料をもってくる時に、自分がその資料や文章のどこに着目し、それをどう再表現し、自分の表現として、あるいは2つの資料のどこに共通性を見つけ、その共通性を自分の表現としていくか、というところにオリジナリティがあるということが、多分この国はまだ理解されていないのですね。
ツールミン(Stephen Toulmin、1922年3月25日 – 2009年12月4日)の「三角ロジック」というものをご存知でしょうか。事実と意見の書き分け、エビデンスと主張を分けるという手法です。例えば社会科の歴史の中学校の授業の中で、「何でこういうことがあったのだろう」という問いがあると、「資料集の何ページにこう書いてあります」で終わるのが、これまでの日本の授業。本来は、その先に、その内容があなたの言いたいことにどう結びつくかという、もう一段階あるはずです。もっと言うと、一つの資料から可能な主張は複数あるはずなのに、そこが一段飛んでしまう。つまり、エビデンスと主張を混同していて、エビデンスを出せば、もうそれは主張になるし、その主張は一種類しかないと思い込んでいるのです。これは、論理ということの根幹に関わる問題です。エビデンスと主張を分けて、エビデンスからこの主張がどういう解釈、論理立てとなるか、ヨーロッパやアメリカなどはきちんとしていますが、日本はやってきていないんですね。
八木事実と主張を分けること、そこをごっちゃにしてしまうと、そもそもロジカルな対話の前提が崩れてしまいます。確かに大事な基礎的能力ですね。さて、ここまで日本語教育における課題についてお話を伺ってきましたが、ことばには、教えるためのツール、という側面もあるかと思います。日本の教育指導の現場における「ことば」についても、その可能性をお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
奈須日本は伝統的に、こどもはもともと良いもので、いろんな力を秘めている、だからこそ内面を引き出す、という教育を世界に先駆けてやってきています。今の総合的な学習の時間とか生活科とかにつながる、日本独自のものとして、日本の教師たちが生み出していますし、その根底には、こどものリアリズムを大切にする、という考え方があります。シュタイナー教育(※2)などは1919年にスタートしますが、その1919年に、実は日本でも奈良女子高等師範学校の附属小学校で、(今の奈良女子大学附属)、こども一人一人に委ねるとか、こどもが自由研究をするとか、今でいう総合的な学習の時間を始めていて、海外から来た視察団もびっくりしたようです。
例えば学芸大がOECDと組んで、日本の授業分析をして、そこでの発話や授業の進め方を解析していると聞いていますが、日本の教育の現場には、こどもの内面、こどもの力を上手に使って、しかもそれで対話的、協働的な学習を進めて、今日教えるべきことにきちんともっていく、という技術があることはずっと前から言われています。少なくとも小学校の伝統的な技術としては、ずっと脈々と存在している。ただ中学校・高校はどうかというと、こどもたちで議論させるとか、一人一人の考えを上手に出させるとかというよりも、先生が言いたいこと、この場で発言してほしいことを話させようとしていて、その点は少し問題です。ただ、それは教員の問題ではなく、大学入試があることが原因です。出口で、要素的知識を暗記で聞かれるから、そういう授業にならざるを得ない。それはアメリカやヨーロッパの場合は、出口が100%AO入試だから、私は何を考え、私は何をしたくて、そのためにこんなことをしてきた、と言わなければならないのです。
大学入試が変わる中で、若い先生がアクティブラーニングに向かっていますが、面白いのは、そういうことをやってこどもに委ねたり、一人ひとりのこどもにしっかり問いかけていくことにより、学びが活性化していくことだと思います。授業をまとめていくために、教員が発問するのではなく、「その子の今」を踏まえて問いかける。そうすることで仲間も「その子の今」に関心をもつとか、「自分はどうなのか」と振り返る、そんな方向に授業が変わりつつあります。そういう授業をすると、こどもも授業の内容により関心を持つし、何より先生にとってもやりがいが生まれる。大学入試という出口が進化する中で、結果的にこどもにとっても受験に受かる力が身につく。高校の先生方もそういうことを今後実感するようになると思います。
日本のこどもたちは、自分の考えをいう時に、帰納(※2)型というか、「まずこういうことがあります、次にそういうことがあります、だからこうです」、と言って、結論の遠いところから、ずっと説明して結論に辿り着きます。いわゆる起承転結みたいな論理です。起承転結は東洋的とも言えますが、海外の人からは「日本の学生は議論をするときにアンドを言う」、という指摘があります。「何とかですアンド、何とかですアンド」と言う。「次にこうです、次にこうです」と。何が言いたいかは、最後まで聞かないとわからない。それに対して、ご存知のように、アメリカの人は演繹(※3)型というか、常にビコーズと言いますね。まず結論を言って、「なぜ私がそう言うかというと、こういうことだから」という形。アメリカの演繹型と日本の帰納型では型が違うわけです。
面白いのは、歴史教育もそうだということです。「何時代があって、次に何時代があって……」、このことがあったから、このことがあったという風に日本では言いますが、アメリカの授業の歴史分析は、「こういうことがありました」「では何でこういうことが起こったのか」と必ず遡ります。第一次世界大戦が終わって皆戦争が嫌だと言ったのに、なぜ第二次世界大戦が起こったのだろうか?とか。ファシズムが台頭してきたから、ナショナリズムが台頭してきたから、と戻っていく。あるいは、大恐慌が起きて、世界経済が疲弊したが、世界経済が疲弊して、なぜドイツだけがファシズムになったのか、それはフランスが無茶な賠償金を要求したから、ダメージが大きいから、と戻る。ビコーズで戻っていく。どっちがいい、悪いじゃないんです。「型」が違う。その事実を理解した上で、日本的なやり方を見つめ直すことが重要ではないでしょうか。
八木西洋の良さ。日本の良さ。それぞれの良さを理解した上で世界に羽ばたく人材を育てていくことが重要になる、ということですね。
奈須今、グローバリゼーションということも人工知能(AI)化ということも、どちらかと言えば、欧米的なロジックとか、レトリックの下で進行していますが、欧米の型ばかりになってもいけないとは思います。とはいえ、その一方で相手の方法を知らないと戦えない、信頼されないということもあります。また、このことは教員の指導や学びの「型」の問題だけではありません。グローバルに活躍する人材育成のため、オーセンティックな学びで実際に社会を変えていくことをめざすとなると、官だけではとてもできることではありません。皆さんの関心事やご専門に引きつけて、こんなことができるんじゃないか、あんなことがいいんじゃないか、とアイデアを出し合っていただければ良い教育につながっていくだろうと思います。民間活力とかいろんな力、いろんな声が入ってこないと、教育はできません。つまり、狭い意味での学校的学力ではなくて、人生を切り拓いていく、一生涯にわたる実力を育てる場づくりのために、いろんなお声やお力をいただけたらなと思います。
ことばをめぐる教育においては、こどもたちには、社会とつながる学びの中で、日本的な、日本語的なものに価値を見出しながらも、少なくとも欧米的な伝統の中にもっているものを知るとか、それを使えるようにすることは、実利的にはやった方がいいでしょうね。むしろ、それに乗ったその先に、逆に彼らがもっていない東洋的な、日本的なものが武器になります。そのためにも、このタイミングで、日本語を中心にしたことばの教育をどうするかを見直す必要があります。日本語と、日本のことばを取り巻く文化の強みと弱みを整理する必要がある、ということですね。今、弱みばかり目立ってきていますが、日本語ならではの強みは当然あります。ただ、それが何なのかが曖昧な気がします。これからのグローバル社会において、それぞれ文化の良いところをバランスよく取り入れた上で、こどもたちには「ことば」をつかって活躍してほしいです。
※1 修辞学
弁論・叙述のための技術を学ぶ学問分野。 雄弁術、弁論術、説得術、レトリック
※2 シュタイナー教育
20世紀初頭に、オーストリア(現在のクロアチア)生まれの哲学者、ルドルフ・シュタイナー(Rudolf Steiner、1861年2月27日-1925年3月30日)によって提唱された教育思想。知的な経路を通じた学習は教育のほんの一部に過ぎないと考え、感情や意志に働きかける総合芸術としての教育を目指す
※3 帰納(法)
類似の事例を元にして、一般的法則や原理を導き出す推論法のこと
※4 演繹(法)
前提となる事柄を元にして、そこから確実に言える結論を導き出す推論法のこと。
奈須 正裕
上智大学総合人間科学部教育学科教授。東京大学大学院教育学研究科博士課程教育心理学専攻を単位取得退学、博士(教育学)。神奈川大学助教授、国立教育研究所教育方法研究室長、立教大学教授などを経て、2005年より現職。新学習指導要領の策定にかかわるなど、教育界のキーマンとして知られる。著書に『「資質・能力」と学びのメカニズム』(東洋館出版社)、『答えなき時代を生き抜く子どもの育成』(図書文化社)など。